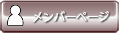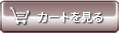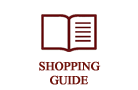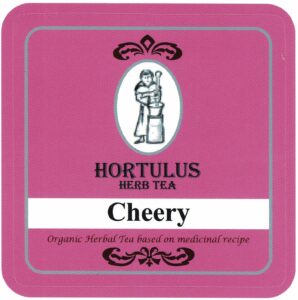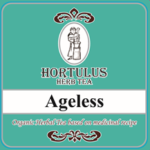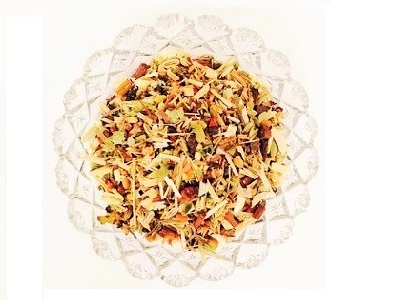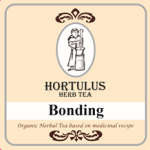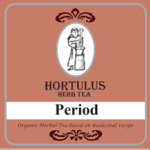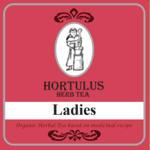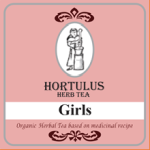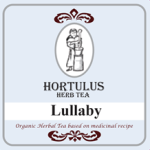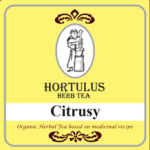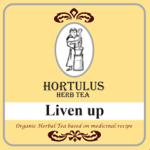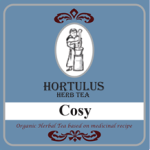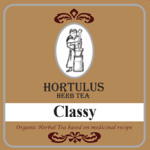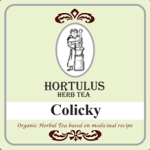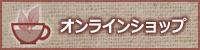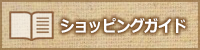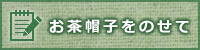作成者別アーカイブ: Hortulus Herb Tea
Cheery チアリー モヤッとしたらやる気スイッチON!
![]() チアリーは仕事や勉強や家事の途中で気分が煮詰まった時、神経伝達機能を活性化するハーブ達があなたのやる気を応援します。ミント、ローズマリーは香り成分が鼻腔から脳へいち早く刺激を与え、微かな苦味がお口の中に心地よく広がるバコパが思考回路の整理をチャチャっとお手伝いします。さらにブルーライトから目を守るカレンデュラと 疲労回復を助けるレモングラスも配合しました。チアリーのティーブレイクでやる気と元気な笑顔を取り戻しましょう!
チアリーは仕事や勉強や家事の途中で気分が煮詰まった時、神経伝達機能を活性化するハーブ達があなたのやる気を応援します。ミント、ローズマリーは香り成分が鼻腔から脳へいち早く刺激を与え、微かな苦味がお口の中に心地よく広がるバコパが思考回路の整理をチャチャっとお手伝いします。さらにブルーライトから目を守るカレンデュラと 疲労回復を助けるレモングラスも配合しました。チアリーのティーブレイクでやる気と元気な笑顔を取り戻しましょう!
Note
❥ 妊娠中の方にはお勧めしません。(ローズマリー)
❥ 授乳中の多量多飲は減乳の可能性があります(ペパーミント)
使用量 1杯分(約180㎖)に対してハーブ茶匙1杯
抽出時間 1分~2分 お好みで
1日1~3杯を目安にお楽しみ下さい。
∞ 蜂蜜を加えたり冷やしても美味しく召し上がっていただけます。
原材料
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
レモングラス Cymbopogon citratus (認定オーガニック エジプト)
バコパ Bacopa monniera (認定オーガニック インド)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
魅惑の妖精とプルートの格下げ
梅雨明けと共に気温はうなぎ上り、日差しが地面を焼きつけるようです。さあ冷えたクリスピーを差し上げましょう。清涼感のある香りと味は体も気分も涼やかにしてくれます。とにかく暑い時期は水分補給が大事です。どんどん飲んで、どんどん出して、体内の水分代謝をよくしましょう。グラスに注いだらスペアミントの生葉を添えますね。手のひらに挟んでパン!さあ、香りが広がりました。お茶を飲みながらクリスピーの主役、ミントにまつわるお話でもいたしましょう。
*****
ミントはシソ科ミント属(Mentha ssp.)の多年草で、ユーラシア〜アフリカ大陸の温帯地域が原産です。紀元前20世紀頃に書かれたレシピに既に載っていることから、それ以前に発現していたことわかります。ミント属は周囲の植物の栄養まで吸い取って枯らしてしまうほどの生命力と繁殖力で雑交配を重ねる為、学名Menthaを冠した仲間は約600以上確認されています。数あるミントの中で、初代はスペアミント(ミドリハッカ、 オランダハッカ、チリメンハッカなどなど Mentha spicataまたはM. viridis)で、葉の縁にみられる鋭く尖った切れ込みから槍=スペア。さすが元祖だけあって他の種類のミントと混植栽培しても最後は全てスペアミントになってしまうほど最強なのです。続いて誕生したのがウォーターミント(ミズハッカMentha aquatica)で、沼地など水の近くを好むことからこの名がつきました。そして初代のスペアミントと後発ウォーターミントの雑交配でできたのがペパーミント(コショウハッカ、セイヨウハッカMentha piperita)で、ピリピリっとした刺激的な風味をペパーと表したようです。
この雑草の如く丈夫で魅力的な香りをもつミント属の学名はギリシャ神話の美少女妖精メンテMentheに由来します。どのバージョンにしても相変わらずコンプライアンス違反な神様の事件簿をご紹介します。
***
その1、冥界の神ハーデスは地上から略奪してきたペルセポネという妻がいながら、地上で見つけた可憐な妖精メンテに心惹かれ、またもや拉致して来て愛人にします。美少女に嫉妬した妻は「お前なんぞ雑草になっておしまい💢」とメンテに呪いをかけ踏みつけにしました。それからずっとハーデスの宮殿の庭でメンテは存在感のある芳香を放ちつつ生きているのですと。
*
その2、冥界の神ハーデスは長い関係を続けてきたメンテを裏切ってペルセポネと結婚してしまいます。嫉妬に怒り狂ったメンテは正妻に罵詈雑言を浴びせ激しい修羅場に!そこへ逆上したペルセポネの母デメテルが駆けつけ参戦、元カノのメンテを雑草に変えて一蹴してしまいましたとさ。罪の意識からか…最低男ハーデスは草になったメンテに芳香を与えたのだとか。
*
その3、本妻ペルセポネは自分と同じようにハーデスに目をつけられ拉致されそうになったメンテを憐れみ、雑草の姿に変えて茂みに隠し、後に元の姿に戻せるようにと目印として芳香を与えました…という美談。元の姿には戻されていませんが?
*
このような神話からミントには人を魅了する媚薬効果があると信じられており、古代ギリシャの男達はこぞってミントの葉を入浴剤にしたり、体に擦り込んだりして女性にアピールしました。一方、禁欲を強いられていた古代ローマの兵士達はミントの使用や摂取が禁じられていたそうな。ミント属も他の多くのハーブと同様ローマ帝国の拡大と共に広められ、9世紀以降はヨーロッパ中の修道院の庭で栽培されるようになり、やがて新大陸へと渡っていきました。今や地球上の温帯地域どこででも見つけることができます。
***
ちなみにハーデスに拉致された妻の姿は、「プロセルピナ(またはペルセポネ)の略奪」(英語では ズバリ“The Rape of Proserpina” )だとか「ハーデス(またはプルート)とプロセルピナ」といったタイトルの絵画や彫刻に見ることができますが、美術の教科書に載せて大丈夫ですか?着衣がない!どころが拉致、強制わいせつ、強姦はそもそも重要犯罪ですし!
***
余談です。ギリシャ神話では冥界の王の名はハーデスと呼ばれますが、後のローマ神話では「プルート」の名で語られます。そして1930年にアリゾナの天文台で発見された太陽系9番目の惑星の名前は、「太陽から最も遠い暗黒の領域にある星に冥界をイメージした」という英国の11歳の少女の発案で「プルート」と名付けられました。命名は一般公募だったのですがが、実はおじいちゃんが天文学者の友人に頼んで天文台に提案し見事採用されたようで…ってコネを使った出来レース?
*
この惑星の発見にちなんで、同年1930年9月5日にスクリーンデビューしたミッキーマウスのペット犬(公式設定では『ミッキーの陽気な囚人(1930年)』に登場する警察犬)は『プルート』と名づけられました。
*
ところが20世紀後半から冥王星サイズの天体が次々と発見された為に、2006年、冥王星は惑星から外されて準惑星(dwarf planet)に格下げされてしまいました。この年アメリカでは「plutoed=降格」という造語が流行語大賞を受賞し話題になりました。その一方で、ウォルトディズニーカンパニーは「プルートは七人の小人(dwarf)達と共にこれからも頑張りますっ!」という粋なメッセージを発信しプルートファンは大喝采!さすがファンタジーの王国。
***
植物としての歴史が最も長い3種のミント、それぞれの使われ方を見てみましょう。
ミントの初代、スペアミントは主に古代よりクッキングハーブとして使われて来ました。イギリスでは9世紀にローマ帝国が持ち込んだ以来、別名“ラムミント”とも呼ばれるように伝統のラム料理に欠かせないソースが作られたり、茹で野菜やフルールサラダ、夏の飲み物には欠かせないハーブになりました。17世紀、清教徒と共にアメリカ大陸に渡ると南西部で商業栽培が盛んになりケンタッキー州は一大産地となりました。
スペアミントとバーボンウイスキーとガムシロップで作る定番のカクテル「ミントジュレップ」は18世紀後半の南北戦争時から飲まれていた記録があります。現在でも毎年5月の第一土曜に開催されるアメリカンクラシックの1つ「ケンタッキーダービー」観戦の伝統として、出走馬入場の際には「ミントジュレップ」で乾杯し、「ケンタッキーの我が家」(KFCのcmでお馴染みの曲)を合唱するのがお決まり。そして優勝馬にはバラの首飾りがかけられるのでこのレースはRun for the rosesと呼ぶそう。なんだかミントの香りと共に華やかな初夏の祭典が目に浮かびますね。ちなみにスペアミントとラムで作るキューバのカクテルはモヒートです。
薬としても古代ローマの博物学者大プリニウス(A.D.23-79)が『スペアミントは香りを嗅ぐだけで元気が出る』と記した通り、イライラを鎮め、疲労感や鬱気分の解消、脳の活性や気付け薬に使われてきました。また穏やかな風味と作用でお子様用ハーブの代表格。疳の虫、お腹や風邪の薬、しゃっくり止めのお茶として重宝されて来た長い歴史をもっています。近年の研究で刺激の強いメントールは0に近く、乳幼児に禁忌な成分も含まないので安全であること、主成分のカルボンの健胃効果、リモネンのリラックス作用、ロスマリン酸の高い抗酸化作用には脳細胞の修復や活性し認知機能の改善し記憶・注意・集中力を高める効果があることが証明されています。またミネラルやビタミンA, Cを多く含みます。
***
次に現れたミントは香りが強いウオーターミントです。中世ヨーロッパでは「ストローイング」といって、ハーブを消臭や芳香、害虫やネズミ避けの目的で床に撒いたりカーペットの下に敷く、といった使い方が流行しました。ウォーターミントはダイニングルームには食欲増進、ベッドルームには安眠目的、とストローイングに最適なハーブとして人気でした。
***
三番目は、初代と後続の自然交配で生まれたペパーミントの主成分は刺激的な清涼感のあるメントールで、こちらは飲食物より民間療法で多く利用されてきました。生葉は頭痛の時に直接こめかみに擦り込まれたり、食後にガムのように噛んだり、風邪や頭痛、生理痛、消化不良の症状緩和や吐き気止めのお茶として飲まれてきました。(⚠️比較的安全なハーブですが妊娠中は1日3杯を目安に飲みすぎには注意です)。ただ、日本人は他の国よりもメントールの刺激的な風味を好む傾向があり、料理や飲み物にもスペアミントの代わりにペパーミントを使うことが多いようです。
*
近年の研究ではペパーミントオイルの有効性も次々と解明され、古来の使用法が証明されています。揮発性の精油成分メントールには殺菌、抗菌、抗ウイルス、発汗、鎮痛、解熱・鎮痒・神経の鎮静・冷却・防腐作用が確認されています。特に胃腸の蠕動運動を抑える効果から粘膜に直接散布できるメントール液製品が開発されており、内視鏡検査の際に副作用が出やすい抗コリン薬の代わりに採用している病院が増えています。またd-メントンの胆汁分泌促進作用が、シネオールの粘液排出促進や免疫アップ作用、アズレンの消化器官消炎作用が確認され、胃薬として有効であることは証明されています。さらにミントポリフェノールには抗アレルギー作用と粘膜保護の働きがあるため、花粉症対策の有効成分として注目されています。
*
ペパーミントオイル配合の製品は数多くあり、胃薬や風邪薬、外用薬として頭痛、筋肉痛、関節痛・肩こりの塗り薬や湿布、虫忌避剤や痒み止めの軟膏や、鼻詰まりや咳止めの塗剤や舐剤のほか、心地よい清涼感と冷感を与える成分としてマウスウォッシュ、歯磨き粉やシャンプー、化粧品、芳香剤など様々な生活用品にも配合されています。
ただし、毒性は低いですが刺激の強い⚠️メントンとプレゴンの含有量が低い製品を選ぶのがコツです。また⚠️乳幼児の顔(特に鼻)に直接塗るのは絶対に避けてください。またアロマセラピーでも精油を使う場合も同様に注意が必要で、⚠️直接肌につける場合はキャリアオイルで正しく希釈されている精油を選んでください。巷にはメンソール(メントール)煙草のED説が都市伝説のように流れ続けていますが、この説に関しては今後も科学的検証を追跡しておきます(2021年夏)。
*****
ミントといえば板ガムよりタブレットが主流の昨今、『ファーストキスは刺激的なペパーミント味?それとも甘いスペアミント味?』 『水金地火木土天冥海?海冥?どっちで覚えた?』と昭和な会話を交わす大人の皆様、暑い休日は冷えたお部屋でプルートの短編アニメシリーズでも鑑賞してみませんか?ディズニーファミリーで言葉を発さない唯一の動物設定のキャラクターですが、実は子持ちで恋多きオジサン犬は人間臭さを感じさせます。降格された冥王星プルートにも想いを馳せつつ、9月5日はプルートの誕生日のお祝いにディズニーランドへ行ってみましょうか。
下積長子さん、ついにブレイク
さて アジサイのお話の続きにお付き合いくだい。アジサイは日本生まれの花でありながら、なぜつい最近になるまでなかなか人気が出なかったのか?そして今やアジサイがおしゃれな花として人気のスターになったお話しでもいたしましょう。
*****
アジサイが人気者になれなかった要因はどんなところにあったのでしょう。そこには3つの鍵がありました。
1つ目は10世紀初頭、昌住という僧侶が編纂した『新撰字鏡(しんせんじきょう)』という日本最古の漢和辞典があります。そこは“草冠に便”と書いて「」なる文字が載っており、意味は「安知佐井」「止毛久佐」と記されています。安知佐井つまりアジサイ、では止毛久佐とは何でしょう?ヒントは室町前期に今川了俊というがまとめた『言塵集』という和歌の参考書的な本に「あぢさゐ 別名またぶりぐさ」と!そう、またぶりぐさは股拭り草、止毛久佐はシモクサと読むのでしょう。いくら別の説があろうとこの文字の並びはどう見てもトイレットペーパーですね…なにしろ草冠に便ですもの。
*
尾籠ついでの余談です。明治4年に日本で郵便制度がはじまると、簡単な木箱に脚をつけて高くした初代のポスト「書状集め箱」が東京12カ所、京都5カ所、大阪に8カ所、東海道の街道筋に62カ所設置され、翌年には全国に設置されることとなります。次世代ポストは黒塗りの大型の木箱に白い文字で大きく「郵便箱」と書かれました。折しも1872年、ちょうど公衆トイレも設置が開始され、おおざとががついた「垂」の文字+「便」の字が続いていたことが災いしてトラブルが多発したのだとか。便の字はどうしてもそちらが連想されがちです。
*
「籌木」なる木片でお尻の始末をしていた古代から江戸時代、いや山間部や島部では20世紀になるまで、植物の葉も同じ目的で使用されていました。その葉の条件、比較的どこでも大量に入手可能、葉が大きく、干しておくと柔らかくなる、アジサイの葉も重宝されたことは想像に難くないです(「蕗」の語源も「拭き」という説あり)。日本では平安時代から紙を使う文化はありましたが貴重品の紙が庶民に行き渡るのは、浅草紙(江戸)西洞院紙(京都)湊紙(大阪)といったエコな「落とし紙」が流通する18世紀半ば以降です。絵画や庭園にアジサイが多く見られるようになった時期と重なります。それまではアジサイの花を見ても「あ〜あれに使う葉っぱの花ね」が邪魔をして、愛でるには至らなかったのでしょうか。不憫です。
***
2つ目は、アジサイは室町時代の頃から仏の供花とされていました。かつて湿気や気温が高くなる梅雨時期には悪い病が流行りやすく、亡くなる人も多かった日本。死者を悼む花として季節の花アジサイが手向けられ、お寺の庭には弔いの意味を込めて多く植えられたそうな。特に疫病が発生した地域では株が増えていきました。それが仇となり、病気を呼び込む縁起の悪い花とされて家の庭に植えることを忌み嫌った家も多くあったそうな。鬱蒼とした庭の薄暗さ、梅雨時期の暗鬱な空気、線香の香り、お寺のアジサイはこんな気配もDNAに取り込んでいたのか、陰気なムードを感じさせる花だったのです。不憫です。
***
3つ目、平和な江戸時代の日本では世界でも類を見ないほど園芸文化が花開いていました。特に将軍の花好きに倣って、江戸の町には日本中の植物が集まってきて、殿様から豪商の旦那衆、武士から町民まで、膨大な量の植木鉢を並べて時間と手間を惜しまず葉や花の形や斑の入り方・色などが他に類をみない奇品を育てることに熱中しました。蘭、椿、蓮、南天など様々な植物が対象にされましたが、代表格は花菖蒲・朝顔・菊が江戸園芸三花と言われています。そんな園芸ブームの中でも、陰気なイメージがあり、丈夫で容易に繁殖するアジサイには誰も価値を見出さなかったのです。不憫です。
***
こうして不遇の時代を乗り越え、戦後になって昭和の高度成長時代ともに観光ブームが訪れると、原産国である日本でも遂に本格的に人気が出てきました。上記のような事情からアジサイを植えたお寺は各地に多くあり、鬱蒼とした半日陰でもしっかりと育つ上、さらに丈夫で根つきの良いアジサイは斜面の土留めや垣根にも多く利用されてきました。開花を迎えると群生したアジサイが一面埋め尽くして咲く絶景が観光雑誌で紹介されると アジサイは重要な観光資源として一気に注目を集めます。真っ先に話題になった北鎌倉の明月院を皮切りに、全国でこぞって株を増やしたお寺が「あじさい寺」を名乗り、次々と名所ができ「アジサイロード」や「アジサイ列車」などを目当てに観光客が押し寄せ大人気になります。もうアジサイからおシモの紙や病死を連想する時代ではなくなったのです!こうしてアジサイは愛でられる花となり、昭和歌謡から平成、令和のJ-po界でも数多く歌われているのです。
*****
現在でもアジサイの花をお守りとしてトイレや玄関に吊るす風習が各地に残っています。アジサイの花の形が平安時代から魔除けのために吊るされる薬(くす)玉に似ていることも由来するようで、いろいろな方法やご利益があるようです。そのひとつに、アジサイの歴史全てが詰まったようなお守りを見つけましたのでご紹介します。アジサイが満開の時期(特に6月の6がつく日がよし)花を一朶(いちだ、アジサイのように小さい花が集まって咲く花の数え方だそうな)紙と紐で(できれば半紙と水引がよし)ブーケ状にし、トイレに逆さに吊るしておくと、生涯お下の世話にならないというお守りです。1年間吊るしたアジサイは感謝を込めて海や川へ流し(お清めの塩と共に新しい半紙で包み燃えるゴミにだしても可)その年に咲いたアジサイを新たに吊るしてまた一年。吊るしたまま放置ておくだけで、色は薄く変化しますが姿は原型をよく留め素敵なドライフラワー状になります。悲しい枯死した姿を見せる他の花との大きな違いです。超長寿時代の切実な願い、ご利益を信じて今年から試してみてはいかがでしょう。
*****
かつて見た映画『ベニスに死す』(1971年・イタリア)で、溢れんばかりのアジサイが華やかに飾られたホテルの場面がとても印象的でした。最近の日本でもアジサイの花はレストランやカフェ、ホテル、もちろん一般家庭の室内や庭をセンス良く飾っています。ガクアジサイも派手やかな手毬咲きともまた異なり、他の花との相性もよく素敵です。もうネガティブな面影はどこにもありません。古代から姿形がそれほど変わったわけではなく、ただ見る人間が持つイメージが変わっただけなのです。今日の主役はまるで下積みの長かった演歌歌手のような「アジサイさん」でしたが、今や大御所スターになれてほんとうによかったです。
***
最後にちょっと冠婚葬祭豆知識。
弔事編:色も青や白い花なら派手すぎず、棘も匂いも花粉もなく弔事に最適そうに見えますが、毒があるので供花や仏花に使用するのは避けた方が無難のようです。もちろん故人やご遺族がお好きなことをご存知の場合は構わないそうです。
慶事編:ボリュームをだして豪華にするもよし、清楚で可愛いイメージにするのもよし、様々な飾り方ができて種類が豊富なアジサイは花嫁さんのブーケから髪飾り、教会や披露宴会場の飾りつけにもぴったりです。花言葉も「元気な女性」「寛容」「家族団欒」などブライダルにはピッタリです。ただし、平安時代から続く「移り気」や「不実」のイメージを気にする方もいますので、参加者がアジサイを身につけて行くのは避けたほうが無難のようです。
*****
こんな梅雨空の今日は、アジサイの葉にアルミホイルを巻いた理科の時間をぼんやり思い出します。さ、冷房が効いた静かな図書館に出かけてみませんか。ぜひ、アジサイ研究の第一人者、日本アジサイ協会初代会長の山本武臣氏の著書『あじさいになった男』(コスモヒルズ,1997) 見つけてみて下さい。アジサイのことがもっと好きになりそうです。
意外に複雑だったカタツムリの友
今日は貴重な梅雨の晴れ間、お洗濯日和と思いきや午後は雷になるとか。気圧の変化に体が追いつきませんね。今モーニングを入れましょう。このお茶は朝の1杯なら浄化に、日々ティーブレイクの1杯でバランス調整に一役かいます。お茶を待つ間、ホーチュラスでは扱いませんが生薬の1つともされているアジサイにまつわるお話をいたしましょう。まず今日は子供でも知っているアジサイですが、花の構造や種類が名前がややこしいこと、アジサイの歴史などからはじめましょうか。
*****
まずご注意から。アジサイの花は生薬「紫陽花(しようか)」として解熱などに使用されますが、毒性のある物質を含むので素人の使用は危険です。アジサイの変種である甘茶(Hydrangea macrophylla var. thunbergii)は生薬としても使われていますし、仏教の花まつりに欠かせないお茶です。他の種類のアジサイと間違えたり、濃く煮出しすぎるとやはり中毒のリスクがありますので、特に小さい人が飲むときは注意が必要です。またアジサイという名のついた中国原産ジョウザンアジサイ(Dichroa febrifuga ) は種属は異なりますが、やばり漢方薬として根を「常山」若枝は「蜀漆」の名で使われています。こちらもやはり毒性物質を含む為、専門家以外の使用は危険です。アジサイはごく身近に在る植物ですが、触ったら必ず手を洗う!間違っても料理に添えない!小さい人が口にしないよう要注意!これはよく覚えておいてください。
*****
アジサイは日本原産のアジサイ科アジサイ属の落葉低木です。初夏に咲く白や青、紫、ピンク色の花は世界中で庭木、鉢花、公園、アレンジメントの花材として見られます。姿形が異なる多くの種類がありますが、全てたった一つの原種、額(ガク)アジサイ(Hydrangea macrophylla f. normalis )から生まれています。ガクアジサイは花房の縁取りにだけ花(装飾花)をつけます。花弁に見える部分が萼(ガク)で、萼の中芯にある豆粒のような蕾から咲くのが花です。この装飾花には雌蕊がなく装飾花に囲まれた「こんもりツブツブの小花」集団のひとつひとつが真花です。真花は雄蕊と雌蕊が揃った両性花で、花後に水壺の形をした小さな実(蒴果)を結び種が採れます。周囲の装飾花もただのお飾りではなく、早めに開花することで虫を誘い両性花の受粉を促す役目があります。属名Hydrangeaは実の形からラテン語で「水+壺」、種小名のmacrophyllaは「大きな葉」、最後尾のf(品種名)normalisは「正規の」を意味します。後述いたしますが、分家が先に登録を済ませていた所為で本家のこちらが分家の名前の最後に品種名を付け足す羽目になりました。
***
清楚な印象のガクアジサイ対し、装飾花だけで花房を埋め尽くすアジサイをホンアジサイ(Hydrangea macrophylla f. macrophylla)と呼びます。原種の栽培種とも言われますが、本来丈夫で野生化や変異、自然交雑を重ねていることから自然発生の可能性も否定できません。装飾花しかない手毬咲きのこちらもDNA的にはガクアジサイと同属同種、花に雌蕊がありません。ただし!数多ある派手なガクを持つ装飾花をよーく見ると、雌蕊雄蕊が揃った両性花が混じっているのです!さらに、密集した装飾花を書き分けると、手毬の中に埋もれて小さな両性花が咲いています!見つけると幸運が🍀、的な話はありませんが、ホンアジサイを見たら是非コソコソっとかき分けて両性花を探してみてください。学名は原種より先にこちらが登録してた為、原種はに一品種名がつけられ登録されました。すると先に登録したこちらには自動的に(命名法の規定に則って)種小名macrophyllaをもう一度繰り返してつけられました。まるで念を押すかのように偉そうに!って、分家が「元祖」とか「総本家」を名乗って本家面するとは、まるで老舗騒動のようですね。
*****
さて、かなり古い時代(不明)に日本から中国へと渡っていたアジサイは、17世紀頃からグローバルな活躍をみせていた「プラントハンター」なる仕事人達によって欧米に持ち込まれると、目を引く豪華な花房、魅力的なバリエーションの多さから瞬く間に人気が出ました。ヨーロッパの各国から放たれこの業界人たちの話は、例の出島の悲恋の真相も絡めて次回また。
***
アジサイは英語でHydrangeaハイドランジアと言います。北米東部には早くからガクアジサイが伝わっていたようで、先住民は自生する帰化種「アメリカノリノキ」の根を利尿薬として使っていました。1739年、この標本を入手したオランダの植物学者ヤン・フレドリック・グロノビウスが、この木にハイドランジアと名を付けました。しかし「植物分類学の祖」であるカールフォンリンネが「属名+種小名」という二部式学名による正式な分類法を確立したので、1753年にリンネ本人がHydrangea arborescenns Linneと自分の名前をくっつけて正式登録します。最近人気の種類「アナベル」はアメリカノリノキから作られた園芸種です。白くて大きな花が見事で、この仲間は土壌によって色が変わることはなく、白から緑に変わるくらいです。
***
一方、欧州の非英語圏ではアジサイのことをオ(ホ)ルタンスとかオルテンシアと言います。この呼称はフランスのフィルベール コメルソンというプラントハンターが、モーリシャス島(アフリカ)で見つけた手毬咲きのホンアジサイに、Hortanse「オルタンス」という当時比較的多く見られた女性の名をつけたのが発端。彼は1771年(頃)オルタンスの形容詞形オルテンシア、という属名をつけてパリに標本を送り登録を試みますが、手毬咲きするホンアジサイもリンネが登録していたガクアジサイと同属同種と判明した為、あえなく不採用。その代わり西欧に渡って品種改良された全てのアジサイをセイヨウアジサイと呼びその学名(Hydrangea macrophylla f.hortensia)の最後尾で品種名になりました。そして多くの国でアジサイの総称として定着しました。この「Hortansia」の語源には二説あり、一つはコメルソン意中の女性の名が由来。しかしその後の検証でその女性が誰かは特定できず未だ謎。もう一つは、この花がフランス行政長官の庭園で栽培されていたことから、古典ラテン語で「庭園」を意味するhortensiusが由来。我がHortulusと同じ語源ということで、こちらを推しておきます。
*****
さて、ここからは古来より身近にあったアジサイが、原産国の日本でどのように生きてきたのか辿ってみます。
*
奈良時代末期に編まれた日本最古の歌集「万葉集」には日本古来の草花が多く詠まれていますが、アジサイはたったの二首だけです。藍色の花が集まって咲く、という意味で集「あづ」+真藍「さあヰ」訛って「あぢさゐ」と呼ばれた説が有力です。当時の万葉仮名は、漢字の持つ意味とは無関係に音だけで字が当てられていて「味狭藍」「安治佐為」などが見られます。
*
現在の漢字表記は唐の白居易(白楽天)によって香の良い紫の花を詠った「紫陽花」という漢詩が由来で、平安時代の源順(みなもとのしたごう)なる学者がこの花はアジサイだと思い込み、「倭名類聚抄 わみょうるいじょうしょう(935年)」という漢和辞典に「紫陽花」=「阿豆佐為」と載せてしまったとか。しかしこの「源順さん勘違い犯説」には冤罪疑惑もあり、未解決です。残念ながらアジサイに芳香はなく、白居易が詠った紫陽花はライラックを指すと考えられていますし、中国ではガクアジサイの装飾花8つが並ぶ様子を 道教の八仙(代表的な8人の神様)に擬えて「八仙花」呼んでいたそうな。
*
平安〜鎌倉時代には、四枚の花弁(にみえる萼)から「四葩(よひら)の花」と呼ばれます。この時代にも詠まれた歌は五つの歌集に一首ずつ確認できる程度で、人気の梅、桜、萩、橘、菊、藤などとは桁違いです。また花の色が変化することから「七変化」とも呼ばれていました。四という数が縁担ぎで嫌われたのか、色の移ろい易さから不実や心変わりを連想させた所為か、貴族にも武士にもあまり好まれる花ではなかったようです。
***
ちなみに青や紫、ピンク系のアジサイが含む色素はアントシアニンで、これが土壌のアルミニウムと結合して発色します。 アルミニウムが多く溶ける酸性土壌では青系に、中性~弱アルカリ性の土壌ではピンク花になります。リトマス試験紙と逆ですね。ちなみに白いアジサイは色素をもたないので土壌が変わっても白いままです。さらに、白でも有色でも開花から咲き進むにつれ色が変化するのは、いわゆる老化現象です。
***
さて中世と呼ばれる時代、大人気だった物語や日記の類には全く登場しません。絵画でも室町時代(16世紀頃)狩野元信「四季花木図屏風 しきかぼくずびょうぶ 出光美術館蔵」の右隻の左端に夏の花として地味に登場で一枚、安土桃山時代に狩野永徳作(と伝わる)「松紫陽花図 重要文化財 京都南禅寺所蔵」で一枚、なかなか芸術の対象にもなリませんでした。
*
江戸中期には金満主義の俳壇とは一線を画し、真の美を自然の中に探求したと言われる松尾芭蕉がアジサイを好んで詠みました。琳派の絵師たちに多く描かれるようになり、特に俳人でもあった酒井抱一の「紫陽花の着物の少女」では愛らしい着物の柄にアジサイが描かれている、この辺でアジサイの扱いが一気に変わった気がします。さらに18世紀に入ると葛飾北斎、歌川広重、伊藤若冲ら大御所達がこぞって作品に残しており、幕末から明治の絵画や文芸作品にも登場するようになりました。
*
大正期に輸入、そう逆輸入された洋花としてのセイヨウアジサイは、当時建てられた数々のハイカラな洋館の庭にもとてもよく似合い、明るく華やかな印象を与えています。そしてついに戦後の日本でアジサイはブレイクの時を迎えます。
あ、お茶が入りました。つづきはお茶を飲みながらにいたしましょう。
名前を覚えてもらえないおしゃれな奴
三寒四温の日々、春の足音はそこまで聞こえてきています。今日は熱々のコージーを淹れましょう。スパイスの香りと焙煎したたんぽぽとチコリーの根が甘く香って、ミネラルたっぷり、身体がシャキッとしますよ。ストレートにしますか?ミルクを入れ?ではアーモンドミルクを試してみませんか?なかなか合いますよ。お茶が入るまで、今日はチコリーのお話でもお付き合いください。
*****
チコリー(英語名chicory、学名Cichorium intybus )は中央ヨーロッパから西アジアを原産とするキク科キクニガナ属の多年生植物です。高さは1mを越すほどに育つものもあり、直立した花茎にはデイジーに似た青い花を次々に咲かせます。その澄んだ青紫色は青い瞳に例えられたり「聖母のブルー」とも呼ばれます。 チコリーの花は7月ごろから秋にかけて咲きます。決まった時間に咲き、次第に色が薄くなって約5時間後にはしぼんでしまいます。規則正しい一日花なので花時計としても栽培されてきました。
***
チコリーにはいくつかの別名があります。「サッカリー」の由来はケルト前史の神話。太陽神は青い瞳のサッカリー(Succory)という美しい女性に恋をし、求婚します。しかしサッカリーは「神と人間では身分が…」と断ります。フラれて激怒した太陽神は彼女をずっと自分だけを見つめる花に変えてしまいました。ルーマニアにもそっくりなお話がフロルリールという名の女性で伝わっています。西欧の神話に登場する神々は、どうも我儘で横暴な神が多いようです…
*
もう1つの別名「ウェグワート(道端で待ちわびる人)」の由来はドイツの伝説。戦地に行ってしまった恋人の帰りを毎日街道沿いで待ち続けたていた娘は、戦死の知らせを受けるとその場で泣き崩れ「チコリー」に姿を変えた。娘の目と同じ美しい青色の花が同じ茎でもあっちを向いたりこっちを向いたりして咲くのは、今でも恋人を探し続けているから。だそうな。
*
フラワーレメディーでは「献身的な愛情を与える」エッセンスとして使われています。また花言葉は「待ちぼうけ」「乙女の涙」「切ない気持ち」など。これらは恋人を待つ健気な少女の伝説を思わせますが、もう一つ「私だけの為に生きて」というのもあります。逆ギレした太陽神の呪いのようで怖いですね。もしチコリーの花をプレゼントされたら…気をつけてください。
***
属名のCichoriumはギリシャ語で『畑』を意味するKichorionが由来で、古代エジプト、ギリシャ、ローマの時代から健康野菜として栽培されていました。葉や花は生または茹でて食べられ、焙煎した根っこはお湯を注いで飲んでいたそうな。ギリシャ人医学者、ガレノス(129ー200年頃)が「チコリーは肝臓の友達」と呼んだように、その薬効も知られていました。 特に最近、この根の健康効果に注目が集まっています。が、根っこのお話は次回までちょっとお待ちください。というのも、ヨーロッパでは古くから馴染み深いこの野菜、日本で正しく覚えてもらうまで難儀した、というかまだまだややこしいままなのです。まずはこの野菜の形と名前を知っていただきたいのです。
*****
今人気の洗わずに食べられるベビーリーフの袋にもチコリーの葉が入っていますし、美しい青い花もお料理を華やかに彩るエディブルフラワーとして人気です。しかし、チコリーの最も特徴的な部分は、白菜に似た10センチほどの若芽です。この小人の白菜を剥がしていくと、ボート型のしっかりした葉が十枚ほど重なっています。もともと苦味の強い野菜でしたが、18世紀末ごろ、ベルギーで日に当てないように白く柔らかく栽培するようになった事で、生でも美味しく食べられるようになりました。サラダボールの縁に飾られたり、様々な食材を載せやすいので洒落た前菜に使われています。また、スープやグラタンに入れたり、オーブンやフライパンで焼いたり、天ぷらにしたり、熱を加えると甘みが出てまた違った食感と味を楽しめます。
*
この小人の白菜をイギリスではチコリー、フランスではアンディーブと呼び、日本では菊苦菜(キクニガナ)という和名がつけられています
***
問題なのは同じキク科の一年草エンダイブ(Cichorium endive)という近似種の野菜があることです。こちらはリーフレタス(キク科アキノノゲシ属)や水菜(アブラナ科アブラナ属)に似たヒラヒラの葉野菜で、日本名は菊萵苣(キクチシャ)です。
このヒラヒラをイギリスではエンダイブ、フランスではチ(シ)コレと呼びます。
*****
ここから海外の混乱が発生。アメリカでは東海岸と西海岸とでは英と仏の文化の影響が異なり、小人の白菜型とヒラヒラの名前が混同されました。日本にも江戸末期から文明開花とともに様々な品物、植物や食品、様々な外国語が一気に雪崩れ込んできました。こうして物の名前、人名、地名など、現地語読みか英語読みかでごちゃ混ぜになり、これは今も続いているのです。こうしてチコリーとエンダイブは混同されてしまいました。
*
令和の現在、野菜売り場では英語読みに則って小人の白菜をチコリー、ヒラヒラをエンダイブ、と表示しているところは多いのですが、フレンチレストランはもちろん、しゃれた輸入食材店ではフランス風に小人の白菜をアンディーブ、ヒラヒラをチ(シ)コレという名前で売っています。イタリアンレストランのメニューでは小人の白菜をチコリーア、この変種はラディチオ、ヒラヒラはインディヴィア…あ、やめておきましょう。とにかく様々な近似種や変種も多く、どうにもややこしいのです。
この混乱は「美味しんぼ」64巻の第二話(雁屋哲著1997コミックス 小学館)にも登場します。口論になるカップルのお話、是非ご一読してみてください。
*****
チコリーの栽培はベルギー、オランダ、フランス、ドイツなどが盛んでしたが、現在日本にはアメリカ産やメキシコ産などが多く輸入され、一年中出回っています。さらに日本でも岐阜や埼玉、北海道でも栽培されるようになりました。国産のチコリーは12月から3月までが旬です。どこかで「小人の白菜」を見かけたらこれがあのチコリーね、と認識してやってください。
満月の名前と馬簾ひらひら
さ、ガードが入りました。召し上がってください。北米先住民の万能薬エキナセアが世に知られるようになった道のり、続けましょう。お茶を飲みながらお付き合いください。
*****
18世紀、北米全体がすっかり欧州各国の植民地になるとますます大量の人間(移民だけでなく更なる労働者としてアフリカ人奴隷の輸入)と、作物と動物などなどが4つの大陸を盛んに往来します。当然、病原体も広範囲に移動して疫病は世界規模で流行しました。コレラ、天然痘、スペイン風邪などの感染爆発が繰り返されていた頃、北米の医療は混迷を極めていました。
*
まず移民がユーラシア大陸から持ち混んできたのは科学的な近代医療と、様々なタイプの伝統医療。そこに新大陸で新たに北米原産の薬草だけを使うトムソン式植物療法が生まれ、どさくさに紛れて胡散臭いニセ医者もたくさん参入します。徐々に淘汰されながら最も人気を集めたのが近代医療と自然療法を統合した医療を目指す折衷派(エクレクティック)でした。その折中派の一人メイヤー医師が最初にエキナセアに注目た人物です。彼はネブラスカ州の(先述のマーロンブランドの出身地と同じ)パウニーという小さな町のドイツ人医師でした。1870年代、世間の白人が先住民を野蛮で下等な人種と蔑むなか、同じ医療を志す者として先住民の知識を高く評価し、敬意を持って彼らに指南を請うたのです。
***
ここでちょっと北米先住民が月毎の満月に付けていた呼び名を紹介します。環境や生活習慣は異なりますが、自然と調和し季節を捉えてきた彼らに同じモンゴロイドの血を感じます。(部族によって呼び方が異なるものもあります)
1月: Wolf Moon(お腹を空かせた狼が遠吠えする候の月)
2月: Snow Moon(雪が降り積もって狩猟が難しい候の月)
3月: Worm Moon(みみずが土から顔を出す候の月)
4月: Pink Moon(ピンクの花が咲く候の月)
5月: Flower Moon(花が満開になる候の月)
6月: Strawberry Moon(イチゴが実る候の月)
7月: Buck Moon(雄ジカの角がどんどん立派に伸びる候の月)
8月: Sturgeon Moon(チョウザメの漁をする候の月)
9月: Corn Moon(とうもろこしを収穫する候の月)
10月: Hunter’s Moon(狩りをする候の月)
11月: Beaver Moon(毛皮にするビーバーを捕る候の月)
12月: Cold Moon(寒さが厳しくなり始める候の月)
***
さて先住民にとってエキナセアは、おでき、腹痛、かぜ、そして大自然の中では命取りになる毒蛇や毒蜘蛛の咬傷に効くという万能薬で、根の搾汁を塗ったり根を噛んだり煎じて飲んでいました。メイヤー医師は自ら毒蛇に足を噛ませてエキナセアを塗り、解毒=浄血作用に確信を得ると「メイヤーの浄血剤」として売り出します。途端に折衷派の医師達が使い始め、白人社会に知れ渡りました。
*
時を置かずエキナセアは大西洋を渡るとドイツで栽培が始まり、ミュンヘン大学が中心となって研究、臨床試験が進められました。抗ウイルス作用や免疫機能に対する作用の有効性や安全性が確認されるとドイツや英国で認められ広まりました。アメリカでサプリメントが興隆するまでの一時期、抗生物質の登場でエキナセア人気が翳ったのに対し、欧州では根強く人気を保ってきました。
*
検出されている複数の薬効成分(多糖類、アルキルアミド、フラボノイド、カフェ酸誘導体など)が多様な組み合わせによって抗菌・抗ウイルス・抗バクテリア作用、抗炎症作用を発揮し、マクロファージを刺激しリンパ球の働きや、IL-1とIL-6の産生、T細胞の増殖を促したり、と免疫機能に作用と安全性が確認されていています。しかし作用のメカニズムはまだ全容解明に至っていません。風邪、インフルエンザ、上気道感染症、尿路感染症、ヘルペス、むくみ、鼻粘膜の乾燥、カンジダ症などの感染症に有効と使われています。 キク科アレルギーのある方は十分な注意が必要です。 またドイツのコミッションE(薬用植物評価委員会)では、結核、白血病、多発性硬化症、膠原病、HIVのような進行性疾患のある方の服用は禁忌としています。
***
エキナセアが初めて日本に輸入されたのは昭和初期、和名は紫馬簾菊(ムラサキバレンギク)。花が下に向かって広がる様子が馬簾(バレン:火消しが振るまといに下がる革製の短冊状飾り)に似ている所から命名されました。奈良県の「平和園」という種苗店から鑑賞用として発売されたそうですが、当時の日本人の美意識では下向きに広がる花が好まれなかったとかで人気が出ず。それどころか、花を毟った後の花床部だけ(ネギボウズ状態)を活花やドライフラワーに使用していたと!なんとも冷たい扱いのままひっそり下積み生活を送ってきました。
*
ところが21世紀になると日本人の好みも変わってきたのか、メタリックな質感と存在感のある大きな花が好まれ、ガーデニングでも切り花でも(花を毟らないオリジナル姿)でも人気があります。紫だけでなく黄色、ピンク、白などなど色も豊富に出回り、花季も長くて寒さにも強く丈夫で鉢植えもOK、人気にならない理由がないです。
*
同時に欧米でのエキナセア人気が注目されるようになり、日本でも薬草として栽培を始めた地域があります。かつて養蚕が盛んだった埼玉県寄居町は桑を無農薬栽培をしていましたが、絹織物業の衰微に伴って桑畑をエキナセアに転用しました。毎年7月にはエキナセア祭りが開催されるなど町興しに一役買っています。また鳥取県大山町でも耕作放棄地対策と景観保全を目的にハーブの栽培が検討されていた当時、豚インフルエンザが流行したことからエキナセアが着目され、栽培が始まったそうです。
*****
この季節はホームセンターやご近所の庭先にもエキナセアの花が咲いていると思いますが、夏のディズニーシーの花壇は多くのエキナセアで彩られていますのでチャンスがあったらぜひ探してみてください。賑やかなディズニーシーでエキナセアを見つけたら、ちょっと北米先住民に想いを馳せてみてください。
ハリネズミの花と侵略の罪
梅雨明けが待ち遠しい午後、ちょっと雨が上がりましたね。あなただけの中庭で深呼吸してください。さ、ガードを淹れて差し上げましょうか。キク科の植物にアレルギーはお持ちでないですね。今までなら寒くなる前にお勧めしていたお茶ですが、今は免疫力が一年中試されている時、ガードでバックアップしましょう。ではお茶が入るまで免疫機能を調整してくれる根っこを持つエキナセアのお話でもいたしましょう。
*****
エキナセア(Echinacea spp.) は北米大陸の中央部、草原の乾いた地域を原産とするキク科バレンギク属の多年草植物です。草丈は30cmから1m程で夏から秋に掛けて直径8cm前後の大きめの濃いピンク色の花を咲かせます。別名のコーンフラワーは花全体に光沢があり、質感がとうもろこしの芯に似ていることから付けられています。中心の盛り上がった花床部に細かな筒状の花が集まっており、その間に無数の尖った鱗片がチクチク生えています。鱗片は下側の額部分にまで続いていて、その様子から属名はエキノス(Echinosギリシャ語でハリネズミやウニの意)とつけられました。花弁に見える一つ一つの花は放射状に開きますが、満開を迎えると下向きになりフラガールのような姿になるのが特徴です。
*
近似種は9種類ありますが、薬効が確認されているのは現在3種類だけです。エキナセア・プルプレア(E.purpurea)は葉に丸みがあり、エキナセア・アングスティフォリア(E.angustifolia)は草丈が低め、エキナセア・パリダ(E.pallida)は花が一際大きく色の薄いのが特徴です。開花時の地上部(葉と茎)と通年の地下部(根茎と根)が薬用に使われますが、地下部からアルコール抽出した液剤(また液剤を使用した錠剤やカプセル)はアレルギーリスクがより低いので、参考にしてください。
***
今や全米サプリメント売り上げNo1、「エキナセアは天然の抗生物質」は常識となり、医学会も注目するエキナセアですが、世に知られるようになったのは20世紀になってからです。きっかけは一人のお医者さんでした。そこに至るまでの時代にちょっと遡ってみましょう。
*
1万年以上の昔、ベーリング海峡がまだ繋がっていた氷河期末期頃のこと、シベリアに到達していたモンゴロイド系の狩猟民族がアラスカ経由で歩いて北米大陸に渡ってきたそうな。彼らは大陸全体に分散し、一部はカリブ海〜南米大陸まで南下して定住しました。それぞれ気候や地形に合わせて豊かな文化を築き、部族間同士の争いは皆無ではないものの、世界で最も平和な暮らしを営んでいた民族といえます。彼らは狩りの道具は持っていましたが武器は持っていませんでした。「人間は精霊が宿る神羅万象と調和して生かされる」という精霊信仰を持ち、空は父、月は祖母、大地は母、四つ足は人々、植物は兄弟姉妹と尊重します。薬草も多く発見し恩恵を大切に使いながら脈々と命を繋いできたのです。
*
古代はどこの文明でも「医療」と「神事」の区別がありませんでした。先住民の各部族にも薬草に精通した賢者「メディスンマン」が一人居て、首長として部族を統治し、霊能者として精霊に祈り、病気の治療を司ってきました。例えば「スマッジ」と呼ばれる薬草の束を燻して場所と人々を浄化したり、スエットロッジと呼ばれるサウナ小屋の中で薬草の蒸気、香り、煙とメディスンマンの祈りの歌が全ての苦痛を癒しました。彼らは文字を持たなかったので、薬草の知識や賢者の知恵など全て口伝で継承してきたのでした。
***
閑話休題。書店で表紙の絵に惹かれて手に取った本は、題名「古井戸に落ちたロバ」(北山耕平/Eagle Hiro著,2011 じゃこめてい出版)、副題は“インディアンのティーチングストーリー・生きることをおしえるはなし”です。近年、彼らの知恵が詰まった言葉は次々と文字に起こされ、育児や人生を導く本として絶賛されていますが、このお話には明快な格言も教訓もありません。たった数分で読み終わるお話ですが、納得。部屋に置いてあるだけでも感じの良い一冊です。
***
コロンブスが北米大陸に上陸して以降、15世紀に本格的な大航海時代を迎えるとヨーロッパ各国から巨大な移民の波が押し寄せます。未知の土地で生き延びようとする白人に対し、先住民は作物の栽培法から命を守る生活の知恵、薬草の知識まで惜しげもなく伝授してやました。こうした無償の好意に応えて先住民族の女性と正式に結婚した心ある白人もいましたが・・・彼らを「言いなりになるプライドのない人種」と見下します。そして…好戦的で土地の所有欲の強い白人は先住民が大切にしてきた大地や川を汚し筆舌に尽くし難い殺戮を始めます。侵略者の攻撃に抵抗したり、侵略者同士の抗争に利用され武器を持たされて殺し合いをさせられた挙句に「攻撃的な野蛮人」と侮蔑されるというなんと理不尽な扱い…
*
ちなみに白人都合で史実を曲げて作られていた西部劇然り、欧米での非白人に対する差別は合法とばかりに堂々と行われていました。1972年『ゴッドファーザー』でアカデミー主演男優賞に選ばれたマーロンブランド(1924-2004)は白人の身で先住民差別に抗議し受賞拒否します。先住民が多いネブラスカ州出身というこで思うところがあったのでしょう。これは西部劇が衰退する契機になりました。彼はトラブルメーカーだったようですが、人種差別運動に生涯協力し続けたというブレない姿勢に拍手!
*
コロンブス御一行様以降、北米大陸の侵略は着実に進みました。何よりも侵略者達がヨーロッパから持ち込んだ様々な菌やウイルス(特に天然痘や麻疹)は意図的ではなかったにしても正に生物兵器、免疫を持たない先住民を効果的に激減させました。生き残った者も痩せた土地への強制移住、農場や鉱山での過酷な強制労働、キリスト教の強要ときて奴隷化されました。こうして北米先住民は世界の他の植民地同様、人権を剥奪され差別の下で生きることを強いられました。
*****
あ、お茶のご用意ができてしまいました!続きはお茶を飲みながらいたしましょうか。お付き合いください。
雷と大正浪漫的美少女に
まだ梅雨前だというのに、もう蒸し暑い日が増えてきました。あれ?お疲れですか?顔色が良くないですね。もしかすると暑さのせいだけでなく貧血気味かもしれませんね。今日は血液を元気にするテンダーを淹れましょう。お茶ができるまでの間、テンダーに入っているネトルのお話でもお付き合いください。
ネトルはヨーロッパから西アジア、北アメリカが原産のイラクサ科イラクサ属の多年草で、シソに似たギザギザの葉をつけ、高さは1m近くまで伸びます。世界中どこでも、山裾、空き地、住宅地、ゴミ捨て場、河原、農道、墓地、薄暗い藪、どこにでも生えている野草です。
ネトル(nettle)という単語は古語(アングロサクソン語)の「針」が由来ですが、現在の英語では“厄介なこと”“イラっとさせる”の意味で使われます。 北欧神話では雷神に捧げられるハーブと位置付けられていて、稲妻を起こしたり鎮めたりする「雷神」のシンボルです。今でもネトルのことを 「雷神草」と呼び「稲妻もトゲを嫌ってネトルの藪には落ちない」という言い伝えから、ネトルを雷除けのお守りにする風習が残っています。
学名Urtica dioicaの属名urticaは、ラテン語で“焼けるような”“痛い”“刺”を意味します。葉と茎に生えている透明で産毛のようなトゲは、構造が皮下注射の針に似ていて、中に炎症を引き起こすヒスタミン、アセチルコリン、セロトニンや蟻酸などを含んでいます。うっかり触れてしまうとチクチクした痛みだけでなく、赤く腫れたり水疱ができてしまうこともあります。これが”英語で発疹”をネトル ラッシュnettle rashと呼ぶ所以です。山の動物や散歩の犬も被害には要注意!山菜採りの人間は厚手の革手袋、長袖長ズボンが必須です。
ネトルのトゲは細く透明なのが厄介です。まず毛抜きを使うのは厳禁!微細な針が切れて皮下に残ってしまいます。最適なのは除毛クリームか除毛ワックス(ない場合は木工用ボンドで代用可)。刺さった所に塗り乾いたらトゲごと剥がします。次のお勧めはセロテープがガムテープ。優しく患部に押し当てトゲを除去します。チクチク感がなくなるまで繰り返し、あとは石鹸を使ってぬるま湯でよく洗浄してください。『かぶれた患部に茎の汁を絞って擦り付ける』というワイルドな方法はよほど手慣れた方以外にお勧めできません。茎の汁に解毒成分が含まれているので正解ですがリスクが高すぎます。乾いたら抗生物質か抗菌剤を塗り冷やしておきます。痒みが続くようなら重曹水またはアンモニア水で毒を中和、それでも辛い場合はとげぬき地蔵ではなくお近くのクリニックへ!
学名の種小名dioicaはギリシャ語で「二つの家」を意味する造語で、5月半ばからつける花はおしべだけの雄花とめしべだけの雌花(雌蕊だけの花)が別々であることを指しています。
ネトルにはタンパク質、ミネラル類、クロロフィル、βカロテン、ビタミン類、 食物繊維などが栄養たっぷりなので春野菜として食べられたり、様々な薬効からお茶として利用されてきた長い歴史があります。痛みや痒みを起こす成分はトゲにだけしか有りません。トゲは乾燥させるか、熱湯にくぐらせれば完全に落ちてしまいますので安全です。今日は血液を元気にする作用にスポットを当てます。
まず造血。ネトルには赤血球中のヘモグロビン の産生する為に必要な栄養素、鉄分や鉄の吸収を高めるビタミンC、葉酸やクロロフィル、タンパク質、ビタミン Bを豊富に含みます。特に『緑の血液』とも呼ばれるクロロフィルは分子構造がヘモグロビンと瓜二つで、中心の核がマグネシウムと鉄の違いだけです。クロロフィルと鉄を一緒に摂ると、クロロフィルのマグネシウムがポロッと消化吸収されると、その空席に鉄がポコっとはまってヘモグロビンに変身!即、赤血球に元気注入!というわけで、ネトルは貧血女子必須の最強アイテムなのです。
次に浄血。クロロフィルが消化によってマグネシウムと分離した後の周りの構造物は、食物繊維の数千分の1という小さな難消化性成分です。これらが小腸大腸を通過する時、微細なゴミや有害物質を見逃さず吸着して血管には流レ出さないように阻止します。また、カリウムやクエルセチンなどのフラボノイドが利尿、排泄を助けます。というわけでネトルが血液をきれいに保つ「浄血ハーブの代表」と言われる理由、ガッテンして頂けたでしょうか。
さて、ここからちょっとネトルに絡んだ絵画のお話です。ジョン E.ミレイ(John E. Millais 1829~1896)の『オフィーリア』(1852)といえば。川に恍惚とした表情の女性が浮いている絵です。よく「ラファエル前派」の代表作と紹介されますが、この会派は19世紀半ばのイギリスで結成された新進気鋭の若いクリエーター集団で、神童と呼ばれたミレイもその主要メンバーの一人でした。彼らは古典偏重の古参からは批判も受けつつも、当代随一の美術批評家、ジョン・ラスキンの支援のお陰で、欧米の美術界に新たな潮流を生み出しました。
シェイクスピアの「ハムレット」に材を取ったこの作品には、数々の植物が緻密に描き込まれています。これは花にメッセージや象徴的な意味を託して仕込むシェイクスピアの趣向の再現です。ネトルもオフィーリアの「痛み」の象徴として柳の木の下に描かれています。見つかりますか?同様にラファエル前派や彼らに影響を受けた多くの画家、作家、詩人達がこの仕掛けを好んで使っています。
22歳のミレイ がエネルギーを注いで製作したこの作品は、当時の写真技術を超える精密さが評価されますが、それもそのはず。実際にロンドンの南を流れるホグスミル川で川岸の植物を写しとる為に5ヶ月も費やした後、ロンドンのアトリエで実際にバスタブにモデルを浮かべて、水中のオフィーリアの姿を描いたという念の入れよう。目を凝らすと銀のビーズ刺繍のドレスが見事です。これもミレイ自ら古着屋で見つけたった4ポンドで買ったアンティークだったそうな。とよく聞くエピソードですが ミレイがバスタブの火が消えたことに気づかなかった為に、冷たい水の中でポーズを取り続けたモデルは肺炎寸前で入院し、モデルの父親から慰謝料と医療費を請求された。の後日談。ミレイは値切った上に示談に持ち込んだのだとか。絵は売却済みだし、しかも資産家のおぼっちゃま君ったら…ちなみにケチなミレイ君は恩人ラスキンの妻ユーフィミア(通称エフィー)と不倫の末に結婚、八人の子供に恵まれます。この略奪婚は当時の社交界のゴシップネタでしたが、映画『エフィー・グレイ』(2014 イギリス)を観る限りは、二人が幸せになってめでたしめでたし。
お話戻って『オフィーリア』のモデルは、愛称リジー(Elizabeth Siddal 1829-62) 。奇しくもオフィーリアの生き様をなぞるような哀しい生涯を送りました。18歳のリジーはロンドンの繁華街にある婦人帽子店で働いていました。当時のお針子さん達は事務、雑用、広告塔として店前に立つこともあり、そんな時に画家のウォルター・デヴェレルに見出されスカウトされます。しかし19世紀の英国では絵画モデルといえば娼婦も同然、帽子屋の店主だって、いくら貧しいとはいえ親は大反対。そこでブルジョアの出のデヴェレル氏は信頼を得る為に自分の母親同伴で説得に成功しましたなぜここまでデヴェレルはリジーに拘ったのか?
リジーは背が高く細身、肌は抜けるように白く、髪は赤毛でした。それまで世間的に好まれていた女性像、血色が良く豊満なタイプとは全く違います。特に赤毛は古くから偏見や差別の対照にされてきました。赤毛は魔女狩りのターゲットにされ、赤毛のアンも『にんじん』 のフランソワも皇室離脱したヘンリー王子も教室でからかわれました。発端は中世の頃にキリスト教の布教活動に、文盲の庶民にもわかるように利用した絵画にあります。ゲルマン地域で広く信仰されていた土着信仰を邪教と貶める為に、北欧神話の神“トール”や“ロキ”を赤毛に描いたり、キリストを裏切ったユダを赤毛に描いたりして、「赤毛は悪者」のイメージを刷り込んだのです。ここで、先述の通り雷神のシンボルがネトルでしたね!
デヴェレルがリジーに拘ったのは、今までの美の基準に一石を投じたかったからではないでしょうか。リジーを画壇に引き入れて4年、彼は26歳で夭折してしましたが、彼の確かな審美眼は現代の世界のアートに脈々と繋がっています。
さて、デヴェレルの「十二夜」(シェークスピア 作品より)に男装姿でデビューしたリジーは、瞬く間に人気モデルとなり、同門の画家であり詩人で手の早いD.G.ロセッティ(1828- 1882)と婚約します。しかし彼はなかなか結婚に踏み切らず、ジェインという人気モデルにご執心の上、他の女性達とも関係を持つという最低男。ジェインがお金持ちと結婚してしまうと、長い婚約期間の末にやっとリジーと結婚します。ところが!彼は人妻となったジェインとW不倫関係になります。彼がジェインをモデルにした『プロセルピナ』(1874)を見るに目力の強い黒髪の女性です。生来病弱だったリジーは夫の不倫に悩み体調を崩しつつも、絵画や詩に才能を発揮しますがドラッグに依存し、心も体も壊していきます。遂に流産を機に過剰摂取で自死。結婚後たった2年、32歳の短い人生でした。ちなみにロセッテイが死ぬまでジェインとの不倫は続きましたが、ジェインが玉の輿に乗った相手とは、ロセッティの後輩だったウイリアム・モリス(1834-96)あの人気のモダンデザインの巨匠です。大正浪漫やアール・デコといったアートの世界 + 奇妙な人間関係にご興味のある方は、是非『評伝 ウィリアム・モリス』 (蛭川久康 著2016平凡社)をお勧めします。一読の価値あり!
彼らが生きた時代、パリ万博(1867)で日本の陶芸や浮世絵が紹介されると、欧米の芸術界にジャポニズムなる運動が巻き起こります。件の女好きロセッティは熱心な浮世絵の蒐集家だったそうな。女性の日常の姿を細長に誇張して描く(当時の日本人ではありえない8〜9頭身!)画風は、ラファエル前派にも影響を与えたと言われています。そして明治大正期の日本文学や美術が、今度はラファエル前派に大きな影響を受けるのです。これぞ逆輸入!それにしても病弱短命だったリジー、竹久夢二のかよわそうな少女達…どうもロマンの薫り漂う美女達は、ヘモグロビン不足の貧血女子に見えます。 ネトル茶を飲むように勧めたかった…
もともと絵画に造詣が深かった夏目漱石も、1900年に留学したロンドンで「ラファエル前派」の思想と絵画に大きく影響されます。ミレイの『オフィーリア』 に着想を得たという『草枕』(1906)をはじめ、『坊ちゃん』『三四郎』『門』『夢十夜』『永日小品』あちこちに西洋絵画のファンタジーが散りばめられています。感想文の宿題のせいで漱石先生への関心を失った方、もう一度チャレンジしてみてはいかがでしょう。
バーバパパも西行さんも
暑くもなく寒くもない、心地よい季節になりました。梅雨が来るまでのこの季節、朝早く外に出て思いっきり深呼吸をしておきたいですね。今日は代謝に良し、デトックスに良し、整腸に良し、リラックスにも良し、のコージーを、植物ミルクでカフェインレスのチャイに仕上げましょう。お茶を待つ間、コージーにも入っているタンポポのお話にお付き合いください。
中国では蒙古タンポポや支那タンポポが漢方薬として使われてきました。古い伝説によると… 裕福な家で育った年頃の娘が、ある日乳房の腫れに気がつきましたが恥ずかしくて誰にも話せませんでした。やがて娘が激しい痛みに耐えていることに気がついた小間使いが、母親に娘の病気のことを告げます。すると母親は激怒し「結婚前の娘が乳房を病むとはふしだらな!」と娘を罵倒しました。娘は身の潔白を証明できず思い悩み、ついに川に身を投げます。ちょうど舟を出していた猟師の父娘が娘を助け、濡れた衣服を着替えさせる時に病に気付来ます。猟師は山で薬草を採って来て煎じて飲ませまると、娘の病は日に日に良くなっていきました。ようやく両親が居所を見つけて迎えに来ます。一緒に家に帰る娘に猟師は残りの薬草を持たせてやりました。家に戻った娘は薬草を庭に植えて蒲公英と名付けました。「蒲」は助けてくれた猟師の名字「公英」は猟師の娘の名前だったそうな。めでたしめでたし。
原名は「蒲公草」で、659年の唐で編纂された「新修本草」という薬草辞典に乳腺炎や化膿性疾患に有効、と最古の表記があります。この辞典は8世紀に遣唐使によって日本に持ち帰られ、奈良〜平安時代の医薬生の教科書として用いられました。当時の写本は京都の仁和寺に収蔵される「仁和寺本」の一つとして、現在は国宝に指定されています。
日本でも健胃・利尿・催乳・解熱、消炎・胆汁促進、肝機能の改善などに処方される生薬とされてきましたが、生薬名は蒲公英。かつては香川県や徳島県で採集された関西タンポポが使われていましたが、近年は生育量が増えた外来種の西洋タンポポも薬用に利用されているそうです。
また平安初期に編まれた日本最古の植物辞典「本草和名」(918年頃 深江輔仁著)では「蒲公草」という名前で和名はフヂナ・タナと記されています。江戸時代には飢饉の際の食糧として栽培が奨励されていたり、また春先に野菜の少ない寒い地方では花は三杯酢、葉、茎は茹で菜、和え物、てんぷらに、茎や根はきんぴらなどに調理されていました。
現在「蒲公英」とかいて「タンポポ」と読みますが、これは江戸期に“医食同源、食が命を養う” を基本に健康維持と食餌療法に使える植物を集めた『『閲甫食物本草(えつほしょくもつほんぞう)』(1671名古屋玄医著) で、タンポポという振り仮名が添えられたのが初めてです。確かに全草にビタミンA・C・K、鉄分、カルシウム、カリウム、カロテノイドなどを豊富に含んでいます。
⚠ただし土壌の成分をふんだんに吸収するので栄養価が高い反面、汚染された土地なら汚染物も吸収しています。野性のタンポポを気軽に食べることはリスクがありますので、安全に栽培されたものをお勧めします。また花部はアレルギーを起こすリスクがあるので生食には注意が必要です。
同じ頃、日本最古の農業指導の実用書『農業全書』(宮崎安貞 1697) や、野菜の栽培法を書いた『菜譜』(貝原益軒 1704)に登場していることからも、今は厄介者の雑草を、わざわざ種から栽培していたことがわかります。
ちなみにフランス料理でピサンリ(pissenlit利尿効果からおねしょの意)と呼ばれるタンポポの他に、遮光で白く育てたバルバパパ(Barbe a Papaパパの髭の意。フランスの絵本「おばけのバーバパパ」も、フランス語の綿菓子も同じ語)という品種があります。軟らかい若葉のサラダは春の到来を告げる一品として有名だそうで、日本にもメニューに載せているレストランがあるようです。
様々な文化が花開いた天下泰平な江戸時代「ハマると身代が傾く三大道楽」と言われたのが「骨董」「釣り」に並び「園芸」です。新種を作り出して一発大儲けを狙う庶民、それらを高額な値段で売り買いする豪商や殿様がいました。朝顔、桜草、菊、椿、蓮と同様、タンポポの品種改良も盛んに行なわれたようです。熱が高まり、赤、黒、青色の花が咲く種や、筒咲・満月・折鶴・紅筆・吹き詰といった粋な名前の品種が作り出され、天保12年(1841)には多種多様な園芸品種を載せた『蒲公英銘鑑』が出版されるほど大ブームとなっていました。
その頃は切り花としても愛でられており、当時の生け花『掖入(なげいれ)』や『立花(りっか)』の実用本に出ていますが、水揚げの悪さは否めなかったようです。戦前までは 200種もの園芸種が継承されていたそうですが、今は途絶えてしまいました。ただ近年、岡山県の総社市内や倉敷市内の関西タンポポの群生地で「筒咲」に似た珍しい品種が確認されたそうです。逞しく生き残った子孫なのか…あなたもどこかで幻の品種を見つけられるかもしれません。
余談ですが、この当時の日本文化の高さを称賛していたイギリスの植物学者がいます。1860年、幕末の日本に初来日したロバート フォーチュンは、日本人の花を愛する国民性を高く評価したのです。荘厳な庭に凝る殿様から長屋の軒下に所狭しと鉢花を並べている庶民まで園芸を楽しんでいることや、鎖国を続けてきた島国でサボテンやアロエ、はたまたイギリス産の苺が売られている光景に驚き、江戸の植木市で珍しい園芸植物を買い求め、さらに各地で庶民の暮らしを体験したことから、リアルに体験した幕末の様々な事件などを自著「Yedo and Peking」(1863ロンドン)に細かく綴りました。翻訳本『幕末日本探訪記―江戸と北京』(ロバートフォーチュン著 三宅馨訳2007講談社学術文庫)で読むことができます。
このフォーチュン氏、実は唯の植物ハンターではありませんでした。彼こそ優雅な紅茶文化と貿易や経済、植民地政策にまつわる黒歴史の中心人物でした。お茶好き、植物好きには興味深い一冊、『紅茶スパイ 英国人プラントハンター中国を行く』(サラ ローズ 著、築地誠子 翻訳 2011 原書房)とてもおすすめです。そうそうもう一人、彼よりちょっと早く来日した、やはり東インド会社絡みの植物オタク、否、有名なドイツ人医師がいましたね。この方のお話は、次回にでもいたしましょう。
タンポポという可愛い大和言葉がいつ発生したかは不明ですが、文字として残されているのは室町時代の国語辞典「節用集(せつようしゅう」(1474年頃)が初めてです。語源については諸説あり、①古語の「田菜」+冠毛の「穂穂」が訛った説、②冠毛の乗った穂の様子がたんぽ(槍の稽古の時に刃を丸く包んで保護した綿球や、拓本を採るときに墨をつけて叩く道具)に似ている説、③別名の鼓草から鼓を表す幼児語タンポンポンから説などなど。きっとどれも正解。タンポポ が身近な植物として親しまれていたことがわかります。
前出の別名「鼓草」もいつから使われていた語なのかは定かでないのですが、江戸時代以前の記述は見当たりません。蕾の形が鼓に見えるとか、蒲公英の茎を千切って両端を裂くとクルクルっと巻き上がって鼓の形になるとか、茎の両端に花を差し込んで鼓に似せたとか言われておりますが、江戸期は子供たちの遊びの発想も豊かだったようです。
タンポポと呼ぶよりも「鼓草」のほうが高尚で文学的に聞こえるのか、また五音で使いやすいからか、和歌や俳句でも春の季語として好まれてきました。筆者としては鼓草というと講談や古典落語の演目「西行鼓ケ滝」を思い浮かべます。西行さんが詠んだという和歌を題材にした噺です。季語としては既に季節外れですが気象庁の定義ではまだ5月は春。今のうちにぜひYouTubeで楽しんでみてはいかがでしょう。お後がよろしいようで。
湯煎鍋と悪魔くん
農神さんと源内さんと日本一の星空を
牛蒡の名前で出ています
バードックとイッパイアッテナ
ゾンビと天使と曼陀羅華
味のジャーマン 香のローマン
正倉院と隠密

春分も近づき、そろそろ桜前線が気になる季節になってきました。三寒四温の時期は体調を調える為に細胞まるごとリフレッシュ、を心がけると良いですね。寒い間縮こまっていた心と体をのびのびとストレッチできるように、今朝のお茶はモーニングにいたしましょう。モーニングに入っているのは前回お話したスペインリコリスですが、今回は東洋のリコリス、ウラル甘草(別名東北甘草、学名glycyrrhiza uralensis)にまつわるお話。お茶を待つ間、ちょっとお付き合いください。 ***** マメ科の多年草であるウラルカンゾウは、中央アジアから中国西北部、モンゴル、中国東北部の乾燥地帯に自生しています。中国でもカンゾウ(甘草)、天草と呼ばれていて薬としての歴史は古く、紀元前2世紀頃の薬物解説書『神農本草書』や治療法テキスト『傷寒論』に鎮痙・鎮痛・鎮咳・去痰・解毒などに処方されています。また、他の薬の副作用を抑える効果から、なんと7割以上の漢方薬に配合されてきました。 * 現在も安中散、四君子湯、十全大補湯、人参湯といった有名な漢方薬のほとんどに配合されています。芍薬甘草湯という漢方薬は、女性特有の病気の治療にも多く使われていますが、救急病院にも常備されるほど筋肉のツレや痙攣に即効性があります。 一方、のどの痛みや咳止め、肺炎に処方される「甘草湯」は、漢方薬としては珍しく甘草が単独で使われていて、外用薬としても痔の炎症には直接患部に薬液を塗布するとよい、とあります。 *** 日本には奈良時代に伝来し、10世紀の書物には「甘草」という漢名に対し「阿末岐」「阿万木」(アマキ)という和名がつけられていたことがわかります。我が国最古の甘草は正倉院の北倉99番に香薬の1つとして現存しています。 * 正倉院とはもともと東大寺の倉庫で、確かな建造年は不明ですが紀元759年以前であることはわかっています。収蔵されている宝物は、光明皇后が夫である聖武天皇崩御の四十九日に東大寺に奉献した品々です。宝物には「夫の遺愛の品が目に入ると幸せな思い出が蘇って泣き崩れてしまいます」という書が添えられていたそうで、きっと仲睦まじい二人だったのでしょう。思わずまだ飾りっぱなしのお雛様の姿に重なりました。 *** さすが当時の奈良はシルクロード東の終点と呼ばれた日本の都、正倉院の収蔵宝物の中には、唐や新羅、東南アジア、果ては地中海沿岸から渡ってきた、世界最高の文化と技術の粋を集めた美術工芸品650点と、貴重な薬物六十種が含まれています。というのも、聖武天皇は体が弱かった為、海外から植物、動物、鉱物を原料とした貴重な薬物が数多く取り寄せられていたのです。これら薬物の名前と用法を綿密に記載した「種々薬帳」に載る60種のうち、甘草を含む約40種類の薬がほとんど変質することなく正倉院に現存しており、貴重な資料となっています。 * また種々薬帳の巻末には、「献納した薬物は病に苦しんでいる人のために使って下さい。この世から万病がなくなり、すべての人が痛みや苦しみから救われ、幼い子供が亡くなりませんように」という皇后の願文がしたためられてあり、実際に光明皇后は人々を救うために施薬院を設置しています。正倉院の出庫記録によれば、この施薬院で桂心、甘草、人参、大黄の4種類の薬が最も多く使われていたことがわかっています。 * 平安時代に常陸、陸奥、出羽国から朝廷への献上品に含まれていたという記録が「延喜式」(当時の法令マニュアル本)にあるので、その頃から東北地方で栽培されていたのではないかといわれています。 ***** 時は天下泰平、八代将軍吉宗の時代、医療が一般民衆にも普及するに従って薬草木の需要が増え、すっかり中国からの輸入に頼っていた為、莫大な金銀が流出します。輸入だけに依存してはいられない、と吉宗は幕府主導で薬種栽培の体制を整えます。 * 吉宗は、まず海外から入手した植物を移植栽培し、生きた図鑑、見本園となる幕府直轄の『御薬園』を充実させます。そしてその見本と同じ、または代替となる自生植物を見つけてくるのが、「採薬師」と呼ばれる人達でした。採薬師制度は奈良時代から続いていて、当時は大陸から来た薬草に詳しい人達がその役目を担っていたのですが、吉宗は「採薬師」を将軍直々の特命係『御薬草御用係』として抱えていました。 * 採薬師達は、日本全国歩き回って自生植物を探索し、見つけてきた植物は御薬園に移植され、増産のための栽培研究をします。見本の輸入植物と全く同種属の植物が日本に自生しているとは限りませんので、良く似た代用植物が採集されたこともありました。それでも植物学的にはかなり近縁の植物が採集されていたことは驚くべきことです。 御薬園の見本は探索の見本になる以外、もう一つ役目がありました。当時、幕府は財政が逼迫していた全国の各藩に、財政再建を目指すために高価で取引される薬草の栽培を推奨しました。これで幕府も輸入超過を防げるし、各藩も潤う、一挙両得!といいたいところですが、世間に多くの薬種が出回ると、偽物も多く出回るのが常。偽物を取り締まる為にも本物を維持しておく必要がありました。 *** 余談ですが、江戸時代の特命『御薬草御用係』は御庭番とも呼ばれました。御庭番といえばご存知、隠密。時には薬の採集の為に全国各地を歩き、時には薬草園で薬草の研究に精を出すという表の顔を持ちながら、秘かに忍びの者として幕府の為に様々なことを探るというの裏の顔をもつ採薬師…忍者が薬草や毒薬にも詳しいことを考えると、なるほど納得です。彼らが残した『採薬記』には薬用となる動植鉱物のみならず、各地の自然、科学、文化、風習にいかに精通していかが覗えます。例えば現在の岩手県釜石近くで日本初の磁石を発見したのも採薬使でした。 * そんな想像を膨らませてくれるのが『薬種御庭番』(高田在子著 青松書院)と、『採薬使佐平次』シリーズ(平谷美紀著 角川文庫)です。江戸時代にタイムスリップして、ちょっとミステリーな旅を楽しんでみませんか。 *** さて、江戸最大の幕府直轄御薬園といえば小石川御薬園。現在の、文京区白山3丁目にある小石川植物園で、東京大学大学院理学系研究科附属植物園にされています。 * この敷地はもともと館林藩下屋敷で、幼い藩主、松平徳松が住む白山御殿がありました。 徳松があの「五代将軍綱吉」となった後、敷地の一部に薬園が造られ「小石川御薬園」と呼ばれるようになります。その後、八代将軍吉宗が白山御殿の敷地全体を御薬園として拡大し、先述の通り見本園として機能していました。同時に園内で栽培した薬草は「乾薬場」と呼ばれる小屋で乾燥させ、調剤もされていました。 *** 暴れん坊将軍と呼ばれた八代将軍徳川吉宗と、名奉行大岡越前と呼ばれた大岡忠相、といえば庶民ファーストの市政改革を多く行った江戸時代最高の行政コンビですが、小石川にまつわる成果を残しています。
|
1722年、小石川伝通院の町医師である小川笙船(赤ひげ先生)が目安箱に「貧困対策として無料の医療施設の設立を」と投書すると、吉宗は忠相と相談の上、翌年にこの小石川御薬園の敷地内に施薬院(養生所)を設立させ、貧しくても治療が受けられるシステムを作りました。
* また、園内には青木昆陽(通称甘藷先生)の碑があります。これは昆陽の提言「飢饉の時に命をつなぐ食料となるサツマイモの栽培を」を受理した吉宗&忠相ペアが栽培研究を命じ、小石川御薬園(他、千葉の2か所)で栽培に成功させた記念です。その後全国にサツマイモ栽培は広まり、多くの人を救うことになりました。おまけに「栗(九里)より(四里)うまい十三里」、江戸から十三里にあたる川越のサツマイモが美味しいと、焼き芋は江戸一番の人気スイーツになり。そしてサツマイモは便秘解消に一役買って江戸女性の美肌に貢献したということです。 *** さて甘草の栽培のお話に戻りましょう。江戸時代の甘草栽培で最も重要な地だったのが甲州です。始まりは1525年、武田信虎が派遣した僧が明国から甘草を持ち帰り、信虎に献上した種株を植えた、という記録が残されています。過去の記述を頼りに、1720年、採薬使である丹羽正伯が塩山塩山上於曽の高野家の屋敷内の茶畑に生えていた10本の甘草を発見します。見分の結果、高野家は幕府御用として甘草の栽培と管理を命ぜられました。年貢諸役を免除されるかわりに、収穫した甘草は幕府への上納と、小石川御薬園に栽培株の供給を行うことになりました。もともとこの地で有力な農家であった高野家は「甘草屋敷」と呼ばれるようになりました。 * 実はその甘草屋敷には『消えた甘草の謎』が残されています。1723年(享保8年)10月駒場御薬園の園監だった採薬師、植村政勝(通称:左平次、吉宗お気に入りの御庭番で正真正銘の隠密)が、高野家に立ち寄った際、栽培されていた甘草を全て掘り起こして持ち帰ってしまったというのです。そのとき高野家に残された甘草はたった3本!なぜ幕府から栽培と管理を拝命していた高野家の甘草が持ち去られたのか? * 以下いろいろな資料から推理すると、高野さん宅で栽培する甘草は 小石川御薬園用の苗と幕府御用達用の薬種として納める契約だった。ところが隠密植村佐平次は、高野さんにおことわりもなく掘り起こした甘草を自分が管理する駒場の御薬園や私製の下総小金野薬園に植えてしまった。ということの様です。だとすれば公務員の業務上横領ですか?いやいや、そこは吉宗お気に入りだった佐平次、事件は隠蔽されたようです。いつの世も同じです。 ***** さて漢方薬として二千年以上も八面六臂の活躍をしてきた甘草、現在、生薬としてだけでなく、日常生活に広く使われています。 * 薬としては甘草の有効成分グリチルリチンから作った製剤が肝機能異常から皮膚炎、関節炎、気管支炎、胃潰瘍など炎症全般の治療薬や、口内炎の薬、目薬などの薬剤に含まれています。 * またドラッグストアの棚の市販薬、石鹸、歯磨き粉、シャンプー、育毛剤、クレアラシルといった医薬部外品の薬用スキンケア製品や一般化粧品にもの配合され、現在最も汎用されている成分といえます。 * さらに近年では、グリチルリチン以外の有効成分、フラボノイドはメラニン生成を抑え、肌荒れ予防効果が、グラブリジンという成分は消炎作用や美白作用がある、と化粧品業界でも注目の成分となっています。 * さらにさらに食品にも「グリチルリチン」「リコリス抽出物」または「甘草抽出物」の表示で、醤油、味噌、練り製品、つくだ煮、漬物、ドレッシング、ソース、からスィーツやソフトドリンクといったどこの家の冷蔵庫にもありそうな食材に甘味料として使われています。きっとこの甘さ、とても身近にあって気付かないうちに誰もが日常的に口にしているはずです。 * ただし甘草抽出物(高濃度のサプリメント)や甘草の長期にわたる大量摂取は高血圧や浮腫み、筋肉障害といった副作用の危険があります。特に妊娠中、授乳中、高血圧、心臓など循環器系の病気、肝臓病、腎臓病、甲状腺の病気がある方は服用に注意が必要です。 *** このように平成の日本で大量使われる甘草のほぼすべてが輸入品です。ほとんどが中国の砂漠地帯に自生する甘草で、乱獲による絶滅、砂漠化による黄砂が問題になってきたうえ、中国国内需要も増加してきているので輸出制限をする傾向がでてきました。そこで現在再び甘草の国産化が急務となってきました。 *** 21世紀に入ると国内での甘草栽培試験が各地で始まり、ここ数年製薬会社だけでなく、様々な企業がぞくぞくと甘草栽培に参入しています。例えばゼネコンの鹿島建設や三菱樹脂、佐賀県玄海町と九州大学の共同開発、また青森県、宮城県、新潟県、島根県、熊本県などでも特殊な栽培法が開発されています。宮城県岩沼市はNPOが中心となって津波被災地での甘草栽培に取り組んでいます。つい最近では製紙業で有名な王子ホールディングスも北海道で甘草栽培に乗り出しています。 * そして元祖甘草栽培の地である甲州市でもその気運が高まってきました。旧高野家では例の佐平次持ち去り事件によってたった3本になってしまった苗を、享保13年(1729年)まで77本まで増やし、明治5年まで「甘草持主」として栽培を続けたそうです。しかしその後甘草栽培は途絶え、昭和初年の調査ではたった数本の株がぶどう畑で、平成2年の調査ではキウイ棚の下に数本生えていただけだといいます。 * 平成23年、ようやく甲州市はこの歴史的な意義をもつ甘草屋敷を中心に、甘草栽培で市を盛り上げようと動きだし、新日本製薬と共同で栽培研究に乗り出したそうです。 * こうして各地で順調に栽培が成功していけば、数年後には国内産甘草で国内需要の全量を賄ったうえに、中国への輸出もできる日がくるかもしれません。 *** 余談ですが旧高野家(山梨県甲府市、JR塩山駅正面)はもともと有力な農家で、そのお屋敷は甲州民家特有の見事な日本建築です。江戸時代後期に建てられた主屋のほか付属建物や井戸や池、石橋から門にいたるまですべてが、1953年に国の重要文化財に指定されています。三階建ての上層階は甘草の乾燥部屋に使われ、採光と通風の為の突き上げ屋根は、この地方で盛んだった養蚕に合わせた建築形式だそうです。 * 今年もこの甘草屋敷を中心に「甲州市えんざん桃源郷 ひな飾りと桃の花まつり」が開催されています。(2017年は2月11日~4月18日開催中)の貴重な雛飾りや、桃のお花見が楽しめるそうです。 ***** そろそろ陽気も良くなってきます。ちょっと塩山まで桃を見に行くのも良し、また小石川植物園に植わった30種類以上の桜を愛でるも良し、甘草栽培に思いを馳せながらお花見、というのもいかがでしょう。小石川植物園近くの播磨坂の桜並木も見事です。 ***** 日本には「甘草の丸呑み」という慣用句があります。甘草の根だってよく噛みしめてみなくては甘さがわからないところから、物事の本当の意味をわかろうとしないという意味だそうです。あまり使われていないこの慣用句、もしよかったら覚えておいてください。 |
ファラオも英雄も好む甘い汁
日本発のヨーロッパの風景
キンボポゴンが救うマンボクサイ村
糸紡ぎと運命の毒草
Ageless エイジレス 若さを維持する対策
40代後半は脳の老化予防対策の始め時です。加齢による脳萎縮は健康な脳でも50代になると明確になりますが、その度合いに大きな個人差が出ます。脳の老化が進むと、姿勢や体の動き、表情といった外見まで老けて見え、生活の質も低下してしまいます。先手必勝、ちょっと早めから自分で出来る脳の保存対策を始めませんか。
Agelessは、認知症が圧倒的に少ないインド古来の伝承ハーブ(アユルベティック・ハーブ)を中心としたブレンドです。健康な脳の老化と認知症とは症状が異なりますが、脳の老化予防は認知症の発症抑制にも有効なのです。血管や脳細胞を活性酸素から守る、アルツハイマー型認知症の原因となるβアミロイドタンパク質の凝集を抑制したり神経の炎症を抑える、記憶力、集中力、情報処理能力を強化する、といった働きを持つハーブを集めました。
脳、血管、内臓、肌、全身の細胞を酸化老化から守って老化を遅らせて体内の細胞の若さを保つことは、外見の若さを維持すること、またその逆も同じです。人生100年時代、ちょうど折り返しあたりから抗酸化抗老化を意識してみましょう。
Note*
❥ターメリック、シナモンにアレルギーのある方はご注意下さい。
❥妊娠をご希望の方、妊娠中のご使用はお勧めいたしません。(ターメリック、ローズマリー)
❥炭酸リチウム剤(躁鬱病などの治療薬)をご使用の方は医師とご相談のうえご使用ください(シャタヴァリ)
❥肝臓に障害がある方は医師とご相談の上ご使用下さい(ターメリック)
❥抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)やアスピリンをご使用のかたは薬効が高まる可能性がありますのでご注意下さい(ギンコ、ターメリック)
お好みで蜂蜜やココナツオイルを少し加えてもお召し上がりいただけます。
原材料
ゴツコーラCentella asiatica (認定オーガニック ネパール)
ターメリック Curcuma longa (認定オーガニック ネパール)
シナモン Cinnamomum cassia (認定オーガニック ベトナム)
ウィザニア Withania somnifera (認定オーガニック インド)
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
バコパ Bacopa monniera (認定オーガニック インド)
レッドセージ(ダンシェン)Salvia miltiorrhiza (コンベンショナル 中国)
シャタヴァリ Asparagus racemosa (認定オーガニック インド)
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
ブラックペッパー Piper nigrum (認定オーガニック インド)
小さな粒の大きな活躍
人生の節目とローズマリー
懐かしい黄色
苦い汁とシェイクスピア
|
|
* また『ロミオとジュリエット』では、ジュリエットの乳母が「あたしが乳首にワームウッドの汁を塗りつけて昼寝をしていると、ジュリエットお嬢様はそれを嘗めなさって大騒ぎでおむずかり、その日からやっと乳離れされましたですよ」と、語ります。日本では今でも辛子やワサビを使う方法もあるようですが…当時のイギリスではワームウッドが使われていたのですね。 余談ですがこのジュリエットの乳母はシェイクスピア作品のなかでも一番の下ネタ好き。シェイクスピアの戯曲にはご存知の通りユーモア、皮肉、残忍、卑猥な台詞が、比喩や隠語俗語を使って大量にちりばめられています。16世紀、芝居というものが教会で宗教や道徳を説く素人の劇から、役者が演じる演劇へと変化した時代です。テーマは意外に三面記事的な人間臭い悲喜劇で、社会風刺やブラックユーモア、娯楽性を交えた脚本と演出があったからこそシェイクスピアは大人気だったのでしょう。シェイクスピアなんて哲学ぶった小難しい台詞や乙女チックな筋書きが…というイメージで敬遠している方、今更、と云わず松岡和子さんの軽妙な訳で(ちくま文庫のシェイクスピア全集)ぜひもう一度読んでみてください。さらに彩流社の『本当はエロいシェイクスピア 』小野俊太郎著は大人ならではの読み方を教えてくれます。 *** 薬としてのワームウッドは「ワーム=にょろにょろした足のない虫」の名に因み、3500年もの昔から古代ローマで虫下しに使われてきました。その後、腹痛やけいれんを抑える薬、リウマチの痛み止めや分娩促進の湿布薬にも使われました。また葉や枝を燃やした灰の軟膏が毛生え薬、ひげを濃くする薬になったという怪しげな使い方もありました。紀元一世紀に古代ギリシャの医師ディオスコリデスが編纂した薬物誌「マテリア・メディカ 」には強壮・食欲増進・解熱といった薬効が記されており重要な薬草の1つとして扱われてきました。現在英国薬草薬局方では虫下し、健胃薬、胆汁促進薬としての効能が認められていますが、妊娠中、授乳中は禁忌、また長期の服用が禁じられています。
* 中世ヨーロッパでは生活用品として、ノミや蚊、ダニ除けに、干した葉を床に撒いたりベッドに敷いたり、袋に詰めて衣類の防虫剤として利用されていました。これも「ワーム」の名だたる所以でしょう。
* ガーデニングでは茎葉や花から漂う甘い芳香、産毛で銀色に光り深い切れ込みが美しい葉が人気の植物です。またキャベツのモンシロチョウ対策、果樹類のガ対策に効果があるコンパニオンプランツとしても利用できます。ただ地下茎から他の植物の発芽を抑制する物質を分泌するので、同じ土で根を張らせずに鉢植えにして近くに置くとよいでしょう。
***** ワームウッド、といえば切っても切れないのがお酒との縁。ホップが普及する以前はビールの苦味付けに使われていたり、消化促進、食欲増進の食前酒(フレーバードワイン)で有名なベルモット(ニガヨモギのドイツ名wermut、古英語名wermodに由来)が作られています。そしてなんといってもワームウッドの名を広めたのは「アブサンAbsinthe」。19世紀のベルエポックの時代にパリで大流行し、「緑の詩神、禁断の酒、悪魔の酒」などの異名で名だたる芸術家達を虜にしました。このアブサンにまつわる甘く危険なエピソードは、またいつか…
|
ウエディングケーキと焼酎?
Assorted Collection No.6 抗酸化
抗酸化とは活性酸素*を取り除き、生活習慣病の予防や老化を抑えることです。 年齢とともに活性酸素の発生量は増え、多量飲酒、ストレス、添加物、タバコ、激しい運動、紫外線なども活性酸素を増やす原因となります。脳から爪先まで全身の細胞に少しでも抗酸化物質を届けたい、そんな方のティータイムに最適な組み合わせです。
| 活性酸素*はフリーラジカルとも呼ばれスーパーオキサイド、一重項酸素、過酸化水素、ヒドロキシラジカルなどの種類があります。
普通の酸素と異なり奇数でペアになれない分子構造をもつ不安定なタイプの酸素です。活性酸素は自分が安定したいが為に周囲の分子から電子を奪い取ってしまいます。これが「酸化させる」(サビさせる)ということで、肌のシミやシワの原因、またガンや動脈硬化・糖尿病・などなど病気の元凶となるタチの悪い酸素です。 |
内容
テンション エイジレス ライブンアップ プロセス クラッシー コージー
タイムとミツバチのご縁

10月も末となりましたが、まだまだスカッとした秋晴れが続かない季節の変わり目。花粉症?鼻風邪?そんなあなたには、またReactionはいかがでしょうか。殺菌作用のある成分を含みますので、風邪やインフルエンザによる咳やのどの痛みにも利用できます。お茶は飲んでも良し、うがい薬として利用することもできます。紀元1世紀に活躍したローマの医学者ディオスコリデスが「タイムとはちみつをあわせたものは胸から痰を排せつする助けをし喘息を治す」と勧めるように、今日は蜂蜜を入れて差し上げましょう。お茶を待つ間、今日のお話はリアクションにも配合されているタイムと素敵な結びつきのあるミツバチのお話をしましょう。 ***** まず一つ目は「タイムとミツバチの刺繍」のお話です。 時は中世11世紀、ヨーロッパではカトリックの聖地でもあるエルサレムをイスラム勢力から奪還することを目的に十字軍の遠征が始まります。東ローマ皇帝は当時のローマ教皇に援護を依頼、教皇は集まったフランスの騎士たちに向かって「乳と蜜の流れる土地カナンを奪還しよう!」という旧約聖書由来の言葉で彼らの心を掻きたてました。しかしこの遠征、ローマ教会の「神の正義のもと」はただの建前で、西側各国の国王、諸侯、商人、農奴らが東方の豊かな土地と経済力に対してそれぞれの欲と野望で攻め込んで行った、無秩序でグダグダな進軍だったのですが…。そんな夫や恋人を戦地に送り出す女性たちはタイムの葉や小枝を贈ったり、彼らのシャツの襟やスカーフに「タイムとミツバチ」を刺繍したというのです。なぜ「タイムとミツバチ」だったのでしょう。 *** タイムは…ギリシャ神話より。大神ゼウスの企てた「増え過ぎた人口は大戦で半減すべし‼」という恐ろしい計画に端を発し、トロイアの王子パリスが毎度お騒がせなアフロディテにそそのかされ、スパルタ国王の王妃であるヘレネーを略奪したことでトロイア戦争が勃発します。長い闘いの末にパリスが命を落とした時、ヘレネーはパリスとすべての勇敢な戦士達を偲んで涙を流します。その涙の一つからタイムが、もう1つからはエレキャンペーンが生えたというのです。(トロイア戦争はいろいろな神や女たちが勝手に頭を突っ込み、目的も見失って下らない闘いを延々とつづけたのですが、十字軍の遠征はこの神話の再現の様に酷似しているのが面白い!) * こうしてタイムは「勇者の印」「勇気の証」と伝承され、古代ローマの兵士たちは勇気を鼓舞するためにタイムの香油を入れた風呂に入ったといいます。当時「あら素敵♥、タイムの香りがするわ💕」というのは男性に対する最高の褒め言葉だったようです。 *** 一方のミツバチ。古代エジプトでは黄金色に輝く甘く栄養価の高い蜂蜜は奇跡の食べ物とされ、「太陽神ラーの涙」とまで崇められていました。そして女王蜂を中心に大きな家(巣)で大家族を作る蜂は繁栄の象徴、幸運の象徴、貯蓄の象徴とされ、女王蜂の姿は歴代エジプト王座のシンボルとして使われました。その流れから「ミツバチ」はヨーロッパではラッキーアイテムとして様々な装飾品やお守りのモチーフに使われてきました。 * そして十字軍遠征でキリスト教徒の心を掴んだ「乳と蜜の流れる土地カナン」というキーワードにミツバチの重要性が隠されています。この言葉は旧約聖書「出エジプト記」の中で、モーゼに率いられてエジプトを脱出したイスラエルの民が、神が約束した「乳と蜜の流れる地」であるカナン目指したのです。旧約聖書の時代、滋養のある食品、乳や蜜は肥沃な土地、恵みと豊かさのシンボルでした。そして蜜を取るミツバチもまた神に下された大切な生物だったのです。
|
* ちなみに西洋でミツバチの他にラッキーチャーム、いわゆる縁起物とされるアイテムは、卵(宇宙の始まり、キリスト教では復活の象徴)、蛇(神の使い、特に2匹が互いの尾をくわえたウロボロスの意匠は∞永遠の象徴)フクロウ(神の使者、知恵の象徴)、蜘蛛の巣(運を捕らえる)、カエル(命の再生、健康と繁栄)などがあります。 *** こうしてラッキーアイテムのミツバチと勇者の印であるタイムは、戦場へ旅立つ者への祈りをこめて一針一針刺されていたのです。 ***** 2つ目は「タイムとミツバチのGive&Take」、上手に持ちつ持たれつ生きている、自然界のシステムについてお話しましょう。 タイムは地中海沿岸原産のシソ科のハーブで温暖なヨーロッパとアジアに自生します。約300以上もの種からなるグループがあり、上に伸び上がるタイプとカーペット状に広がるタイプがあります。基本種のコモンタイム(Thymus vulgaris)は立ちあがるタイプで、古くから料理や薬用とされ日本名はタチジャコウソウ。 * 初夏から秋にかけて咲くタイムの花は、雄花の時期と雌花の時期がある雌雄異熟というタイプです。まず雄花として開花しますが、雄しべが花粉をつけている間の雌しべは閉じていて自家受粉を避けています。そして雄しべは花粉がなくなると枯れ落ち、そのタイミングで雌しべの柱頭の先が開いて雌花となり、これで受粉可能状態。これは近親交配による遺伝的組合せのバリエーションの低下で種の存続の危機を避ける為です。ミツバチや蝶が花に潜ってモゾモゾと無我夢中で蜜を吸っていると頭や背中にはたっぷり花粉が付き、そのまま移動すると本人が知らない間に運び屋をやることになります。この作戦、虫に花粉の運搬を任せることで自分の遺伝子を出来るだけ拡散したり、優秀な子孫を残す為に植物が仕組んだ秘策なのです。 *** ミツバチや蝶にとって、タイムは運び屋代行の代償と美味しい蜜をいただけるだけではなく、プラスαのメリットがあるのです。 * タイムはフェノールの一種で強い抗菌・防腐作用を持つチモール(thymol)という有機化合物を多く含みます。この作用から古代エジプトでミイラを作る時に使われたり、冷蔵庫のなかった時代には大切な天然の保存料として食品を守りました。紀元前1世紀のヒポクラテスもその殺菌効果を書き残しており、中世ヨーロッパで疫病が大流行した時にもタイムは大活躍したのですが、そのエピソードはいつかまたの機会にお話しましょう。 * さてさて、その殺菌作用がミツバチにも恩恵をもたらすのです。例えばミツバチの天敵「ミツバチヘギイタダニ」が猛威をふるった時、被害の少ない地域にはタイムが自生していたそうです。ローマの詩人ホーレス (65 BC – 8 BC)は、紀元前一世紀のローマで、既に養蜂の為にタイムを栽培していることを書き残していますので、その頃から養蜂家の間ではタイムが大切な植物とされてきたことがわかります。 * 現在もタイムから取れるチモールは、ダニに対して効果的であると同時にミツバチに高い安全性があることも 確認されていて、ハチにとっても養蜂家にとっても有りがたい天然の薬として使われているのです。 ***** この時期、まだ花を付けているタイムを見つけたら観察してみてください。花に潜って背中に花粉を背負っているかわいいミツバチをみつけたら、トロイア戦争と十字軍、遠い昔のから騒ぎに思いを馳せてみてください。
|
女神と,たくさんの父達と,血走った目

涼風と共に空の青も透明感のある濃い瑠璃色へ変わってきたこの頃、自然の中でお茶を飲むのも気分が良いものです。それなのに…春と同様、秋もティッシュ片手に窓を閉め切って過ごさなければならなくなるあなたには、今日からReactionを毎日差し上げてみましょう。炎症が起こる前から、が鍵です。今日はそのリアクションに入っているアイブライトにクローズアップです。 ***** アイブライトは北ヨーロッパ原産のゴマノハグサ科、半寄生の一年生植物です。牧草地や荒れた土地に生えているイネ科やカヤツリグサ科の植物の根から養分を吸い取って成長し、夏から秋にかけて淡い紫を帯びた白い唇形の花(1~2cm)を咲かせます。小さな米粒のような花から和名は薬用小米草(やくようこごめぐさ)。日本で多くのコゴメグサの変種が東北から九州までの山間部の草地に生息していています。 *** アイブライトの学名(Euphrasia officinalis)は、ギリシャ神話の「三美神(カリテス)」の一人、エウプロシュネに由来。ちなみにカリテスはカリス(女神)の複数形、ギリシャ語で神の恵みとか恩恵を意味する語、巷で耳にする「カリスマ」の語源です。 * アイルランド地方には「盲目の少女が毒草に触れそうになった時、エウプロシュネがとっさに魔法を使って目が見えるようになる薬草に変えた」という言い伝えがあります。 * 三美神はゼウスの娘達ですが母親は諸説ありますがエウリュノメもしくはヘラとも…神様の世界、そのあたりあまりこだわりがないのでしょう。エウプロシュネ(祝祭、喜び)、タレイア(花盛り)、アグライア(光輝)の3姉妹は愛と美と生殖の女神アフロディテの侍女として仕え、神々の宴で優美な輪舞を披露するのがお仕事。ボッティチェッリやラファエロ、カノーヴァなどなど多くの絵画や彫刻のモチーフになっています。 * 三美神に関しては相反する「愛欲」と「貞節」に「美」が調和もたらしている女性の内面を表現している、とかなんとか異説だらけです。並び順にも統一がなくギリシャ神話にも無関係、これはどうも単に作品に後付けされた解説なのでしょう。 多くの作品は3人揃って大胆な全裸 (神の世界はおおらかです)で踊る姿が描かれていますが、レオナール藤田(嗣治)の三美神はそれぞれの様子が全く異なり、一人ずつの個性をわかりやすく見せています。三美神の作品を見かけたら、どれが誰で、何の象徴なのか想像を巡らせつつ裸体鑑賞、美術鑑賞をするのも芸術の秋にはまた一興かもしれません。 ***** 太古よりアイブライトは心を研ぎ澄まし霊力を高めるハーブと考えられ、目を閉じて抽出液を浸した布を瞼に載せると相手の嘘を見抜けると信じられていました。 * 薬として紀元前一世紀、眼の感染症に初めて、古代ギリシャの植物学の父テオプラストスが目薬として処方した記録が既に残されています。同時期、医学の父ヒポクラテスや、ちょっと若い薬物学の父ディオスコリデスも「目にはアイブライト!」と記しています。 |
ちなみにテオプラストス、本名はティルタマス。学者仲間だったアリストテレスとプラトンが彼の理路整然とした弁論術を称えて神(テオ)のごとく語る(プラストス)という意味でつけたニックネームだったのです。実は当時の著名な学者達は皆、「あだ名」や「ペンネーム」で活動していたようで、あだ名を付けたアリストテレス本人も、そもそもが本名ではなかったようです。
* 時代は下り16世紀後半のイギリス、エリザベス1世の時代にはアイブライト・エール(ビールの一種)が飲み物として流行していたり、喉風邪の薬としてアイブライトのタバコが喫されていました。17世紀、博物者で医師で修道女、ドイツ薬草学の母ヒルデガルドの提唱で、疲れ目から白内障まで「目でお困りの時はアイブライト」と周知されていきました。 * 当時の詩や小説にはアイブライト入りの白ワイン、紅茶、シチューを飲むシーンやアイブライトの洗眼・点眼薬が出てきます。不朽の傑作と謳われたイギリスの一大叙事詩『失楽園』の中では、禁断の実を食べて楽園を追われ失明したアダムに対し、『大天使ミカエルはアダムの眼をアイブライトとルーで洗い流し、光をとり戻させた』とあります。しかし作者ジョン・ミルトン自身は作品書く前に視力を失っていたそうですから、アイブライトに失明を治す効果はないのでしょう。 イギリス植物療法の父カルペパーは、「もしアイブライトがもっと利用されれば、眼鏡屋の半分は倒産していただろう」と書き残していて、フランスではCasse Lunette「めがねの壊し屋」という別名も持っているほどでした。 ***** さて、古代医療から中世まで延々と多くの医科学の父と呼ばれる人たちが、ハーブを使う根拠としていたのは、「植物の色、形、生育場所などが、似た臓器や作用に関係がある」という説。アイブライトも白い花びらの中に黄色の斑と紫色の脈が浮かんでいる様子が、疲れて血走った目に似ていることから目を癒す効果を与えられていると考えられていたのです。 * この「見た目の特徴と効能」の考え方は、16世紀初頭、医師で錬金術師であるパルケルススがDoctrine of Signature(象形薬能論)として確立した理論は、「神はあらゆるハーブの姿形にその作用や効能を表すヒントを標し与えているのだ」と、一般民衆にわかりやすい言葉で植物と化学が結び付けました。 奇しくも漢方にも植物と人体を結びつける「相似の理論」という似た考え方があります。現代人としては化学的にどうなのかな?と疑問を感じますが、あながち的外れでもないのです。 確かにアイブライトには消炎効果、収斂効果、毛細血管を強化し、血流を改善する効果、強力な抗酸化作用がある成分が確認されていて、目だけでなく鼻や喉のカタール症にも使われています。ほかにも、胆汁と同じ黄色い花のタンポポや黄色いウコン、丸い葉の形が子宮頚部に似たレディースマントル、葉が病気に侵された肺に似た形をしているラングウォートや二葉に別れたイチョウ葉、擦ると赤い血のような液が出るので外傷に良いとされるセントジョーンズウォート、脳に似た形のクルミやイチョウ葉など形と効能が一致するものも少なくないのです。 *** 偶然なのか神が与えた必然なのか… 臓器や体の部位に似た形を持つハーブ、意外に多くあるものです。散歩や山歩きのついでに見つけてみませんか。 |
美容マニアのローゼルフラワー

猛暑日続きの夏でしたが急に気温が下がり、夏の疲れが出ていませんか。きょうはクエン酸とビタミンCたっぷりのルビー色のお茶、ハイビスカスとローズの花弁、蕾、実などを合わせた「クラッシー」を入れましょう。まだまだ暑さが残る午後はアイスで飲むのが最適ですが、今夜のように安らぎを感じる夕べには、ぜひホットで。 ***** 今日の主役は「クラッシー」の赤の主役ハイビスカス。といっても、フラダンスやアロハシャツをイメージする南国に咲く園芸、鑑賞用の大輪の花(Hibiscus rosa-sinensi)ブッソウゲ (仏桑華)とは異なる種、ローゼルフラワー(Hibiscus sabdariffa)。小ぶりな白または薄い黄色の花は中心部にむかって濃いワインレッド色、茎は紫色の物が多いです。 ちなみに「ハイビスカス」はエジプトの女神「ヒビス」に由来、という情報は誤りです。(ヒビスという女神はいません) ハイビスカスという単語はもともと、紀元後1世紀の植物学者ディオスコリデスがタチアオイにつけた名前でしたが、多種多様なアオイ科の園芸種群全体を指す総称となってしまいました。 * ローゼルフラワーの原産地はエジプト南部のアスワンで9-11月頃に開花します。赤く熟して肥厚した萼を(苞も一緒に使う場合があります)を乾燥させてお砂糖と一緒に煮た「カルカデ茶」が3000年~4000年も昔から飲まれており、種子や葉は食用、茎は繊維に利用されていました。 シルクロードを経てアジア諸国にも伝来し、生薬名「洛神花(ロウシエンファ)」として中国や台湾でも薬として、お茶やお菓子にも使われています。 * 現在でもカルカデ茶はアフリカ大陸の北西部で日常的に飲まれていて、カイロなど大きな市街地のカフェでもお茶といったらカルカデ茶、特にアルコールを飲まないイスラム系の方たちは朝も昼も夜もカルカデ、結婚式の乾杯もグラスに注がれているのは真紅のカルカデ茶なのです。 *** カルカデの赤色はアントシアニン系色素(ポリフェノールの一種)で、強力な抗酸化作用とACE阻害作用があり高血圧症や心臓病に効果があるとされています。梅干しや赤紫蘇と似た味がするのもそのはず、同じ植物酸(クエン酸や、リンゴ酸など)を含んでいます。ミネラルも多く含むので代謝を促し疲労回復や細胞の再生を促す天然のエナジードリンク、美容ドリンクといえます。特にカルカデのクエン酸がローズヒップの豊富なビタミンCの吸収を高めるので、この2つのハーブはゴールデンコンビといわれています。
|
また糖分と一緒に摂ると筋肉に貯蓄型の糖(グリコーゲン)を素早く補充できるので、お砂糖と煮るというのは疲労回復の為に理に適った飲み物だといえます。古代エジプト時代にピラミッドを積み上げた労働者たちも、疲労回復と水分補給のためにカルカデ茶が振舞われたといわれていますし、伝説のマラソンランナー、エチオピア出身の裸足の英雄、アベベ選手はマラソン中の水分補給にカルカデ茶を飲んでいたことで有名です。
*** 古代エジプトの富裕層は男女を問わず美容に関する関心が非常に高く、男性も肌艶を良く見せるオレンジ系のファンデーションを塗り、アイメイクとマニキュアも施すのが普通だったようです。アイシャドウやアイラインは目力を際立たせる効果も狙っていたとは思われますが、緑色のマラカイトは毒性があるので虫除けや魔除けに、碧いラピスは日よけ効果があると信じられ、これらの石を砕いて膠と混ぜて塗っていました。また既にウィッグの技術も進んでおり、男女どちらも様々なヘアスタイルを楽しみ、宝石の髪飾りにも凝っていました。クレオパトラのあの特徴的なボブスタイルもカツラだったという説が有力です。驚くことにエジプト王家の墓から金の糸がたくさん発見され、当時すでに肌の張りを蘇らせる美容整形、金の糸を埋め込むフェイスリフトが行われていたことがわかったそうです。 * 紀元前69年、この古代エジプト最後のプトレマイオス朝の王女として生まれたクレオパトラⅣ世が比類なきビューティーマニアになるのも当然です。バラの香油やミルク、死海の塩を入れたお風呂を楽しみ、蜂蜜と蜜蝋と砂糖を練り合わせたワックスや青銅の剃刀でムダ毛の処理し、肌や髪、爪はオリーブ油やごま油、バラの香油やアロエの搾り汁で保湿。また美容に良い食品にもこだわり、蜂蜜やローヤルゼリー、デーツ、ルッコラ、ゴマ、豆、モロヘイヤなども各地から取り寄せて積極的に食していましたが、究極は真珠です。クレオパトラはアントニウスと富と権力を競い合う晩餐会で自分のイヤリング、大粒のパールを一粒砕いてワインに入れて飲みほして見せたというエピソード。真珠には美容に効果的なミネラル類や、アミノ酸などが豊富に含まれていますので、この場のパフォーマンスとしてだけでなく日ごろから飲んでいたのかもしれません。 *** クレオパトラが美容にもよいカルカデ茶を飲んでいなかったはずはないと思いますが、庶民や奴隷と同じカルカデ茶をそのまま飲んでいたとは考え難いとは思いませんか。もしかすると彼女が何よりも愛した高価なバラやローヤルゼリー、豪奢の極みである真珠の粉を加えたスペシャルドリンクを飲んでいたのかも…と想像が膨らみます。 |
夏は怪談
 夏休み真っ盛り、今年の酷暑は特別です。こんな暑い午後にはミントのお茶をオンザロックで。 口の中からスーッと涼やかになり、暑さ負けでムカムカ、食欲がない時も助けてくれます。でも今日はミントのお話ではなく、ホーチュラスでは扱っていない毒草のお話です。 夏休み真っ盛り、今年の酷暑は特別です。こんな暑い午後にはミントのお茶をオンザロックで。 口の中からスーッと涼やかになり、暑さ負けでムカムカ、食欲がない時も助けてくれます。でも今日はミントのお話ではなく、ホーチュラスでは扱っていない毒草のお話です。
***** 雑司ヶ谷四谷町の御先手組同心、民谷家のひとり娘、岩の婿として養子に入った伊右衛門は、やがて新しい仕官の口に目がくらみ、上司である与力の伊東喜兵衛が孕ませた妾と一緒になることを画策。邪魔になった岩はおりしも産後の肥立ちがよくない。伊右衛門は血の道の薬と称して毒を飲ませ、けなげにも飲みつづける岩、やがて目は腫れあがり髪の毛がばさっと抜け落ち、見るも無惨な苦悶の表情で絶命…裏切られたことを知ったお岩さん、怨めしや不実な夫を祟り殺したのでした。 * 歌舞伎や落語で語られるこの「東海道四谷怪談」は勿論フィクションで、史実としてのお岩さんは美人で働き者。夫の伊右衛門さんと仲睦まじく、格式は高いものの経済的には困窮していた田宮家をなんとか支えるべく屋敷神を信仰しながら奉公に励み、お家は立派に再興した。この噂を聞き付けた人々が田宮家の屋敷神を参拝に訪れるようになった。ということです。これが現在、新宿区四谷左門町の元田宮家の住居跡にある「お岩稲荷」に刻まれた由来です。 * いつ世も、人の成功は世間の妬みを買うもの、田宮家の美談を嫉んだものか、武家社会に対する町民の皮肉なのか…怨霊話にすり替えられまことしやかな俗説として流布された噂。鶴屋南北はこの噂話と当時実際に起こった殺人事件からヒントを得て『東海道四谷怪談』を書き上げたとされています。脚本では田宮家に配慮し、お話の舞台は雑司ケ谷四谷の民谷家とし、さらに田宮又左衛門を元赤穂藩士、妾を押し付ける与力を吉良家家臣と設定し、この怪談話を「仮名手本忠臣蔵」のスピンオフとして交互に場面転換する形で上演されました。1825年 (文政8年) 江戸は中村座での初公演を記念して7月26日は「幽霊の日」だそうです。 *** 余談が長くなりましたが、怪談話でお岩さまが飲まされた毒薬が今日の主役、「附子(ぶす)」でした。附子の毒は舌がしびれ呼吸困難や麻痺などを起こさせ、お岩さんさながらの形相で死に至らしめる…ここから「ブス」という言葉が現代も独り歩きしています。 |
「附子」は、花の形が舞楽の装束で被る鳥兜に似ていることに由来した毒草トリカブトの根から取れます。トリカブトの毒成分はジテルペン系アルカロイドの一種アコニチン、青酸カリの10倍の威力を持ち解毒剤がないので一度致死量を口にすると確実に死に至らしめるつといわれる猛毒中の猛毒、植物界最強の毒と言われています。トリカブトの毒は根に最も多く茎、葉、花、蜜を舐めるは危険です。*****「附子」といえば教科書にも載っている狂言の「ぶす」。一休さんのとんち話「水飴の話」と同じく鎌倉時代に編まれた『沙石集』という仏教説話を基に作られていますが「舐めると死ぬ毒」という意味で「附子」というラベルを貼ったというくらい有名な毒の代名詞だったことがうかがえます。
*** 遡ること「古事記」や「日本書紀」によるとヤマトタケルノミコトの息子はじめ多くの皇族や豪族がこの毒を盛られたり毒矢で殺されています。その後綿々と続く忍びの世界でも重要な武器として伝えられていますが、アイヌ民族も古くからトリカブトの根を煮詰めた毒を塗り込んだ毒矢を狩猟に使っていたという記録が残っています。ちなみに、現在の静岡県東部はかつて「駿河」と呼ばれていましたが、この地域にもトリカブトが群生していたためアイヌ語でトリカブトを表す「スルク」が語源とも言われています。またその駿河の国の富士山、今も落岩の音が絶えない立ち入り禁止の危険地帯「大沢崩れ」にはトリカブトが多く自生しているとか。「附子」からブシ→フジ→富士山という一説もあります。 *** ぶすとぶし。これは毒で使う時は「ぶす」、薬で使う時は「ぶし」と読み分けているのです。漢方では今でも鎮痛・強壮・昂奮・新陳代謝向上の生薬として用いていますが、これは弱毒処理(修治)されています。さらにトリカブトの子根を用いたものが附子(ぶし)、母根を用いたものを烏頭(うず)と区別しています。 ***** 7月から9月の暑い時期に花を咲かせるこの毒草、英語名はアコナイトまたはアコニット(Aconitum napellus)。ギリシャ神話の中からすでに毒薬の代名詞にもなっていて、ヨーロッパからインドにかけて黒い伝説、不吉なエピソードが多く語り継がれてています。こちらはまたいつかお話しすることにいたましょう。 ***** げに恐ろしきは人の怨み、妬み、嫉みに逆恨み… 最近、体調が悪かったり髪が抜けたり…もしかすると最近ビールの苦さがきわだってきていたり… …人の恨みに心あたりがありませんか? |
パッションフラワーはメカニカル
ラベンダー いつからこんなに
Tender テンダー 滋養強壮ティー
Tender テンダーは心身の機能を支える*栄養素を幅広く含むハーブ達を配合した滋養強壮ティーです。病後の回復期や緩和ケア中、虚弱体質や加齢にともなう食欲不振、消化不良、栄養の吸収力不足、貧血、顔色が悪い、冷え、倦怠感、ストレス、活力減退、抵抗力の低下が気になっている方、何となく調子が悪いという不定愁訴でお悩みの方などにお試しいただきたいお茶です。特に血液を元気にするミネラル成分が豊富ですので生理直後の貧血女子にも最適です。
*ビタミンA, B群, C,E, K、ミネラル類(ケイ酸、カルシウム、マグネシウム、カリウム、リン、ナトリウム、鉄、亜鉛、セレン、マンガン、)アミノ酸、食物繊維(ベータグルカン)、植物性ステロール、多糖類、といった豊富な栄養素のほか、スーパーオキシド消去酵素、ケルセチン、アルカロイド、サポニン、フラボノイド、カテキン、タンニン、テルペノイド、セスキテルペン、ステロイドラクトン、ガラノラクトン、クマリンなどいった成分を含みます。
note:
❥ グルテンアレルギーのある方はご注意下さい。(オーツストロー)
❥ シナモンアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 妊娠中の方はご使用を避けてください(シナモン、カルダモン)
❥ 胆石、胃潰瘍や逆流性食道炎のある方や抗凝固剤をご使用の方(シナモン、ジンジャー)、
病気加療中、服薬中の方は医師とご相談の上ご使用下さい。
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
内容
ウィザニア withania somnifera (認定オーガニック インド)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
ルイボス Aspalathus linearis (認定オーガニック 南アフリカ)
ジンジャー Zingiber officinale(認定オーガニック ネパール)
カルダモンシード Elettaria cardamomum (認定オーガニック インド)
シナモンチップ Cinnamomum cassia (認定オーガニック ベトナム)
ネトル Urtica dioica folia (認定オーガニック エジプト)
ペオニー Paeonia lactiflora (ワイルドクラフト 中国)
Bonding ボンディング 母乳促進と産後鬱の予防
♠ボンディングはお母様のご使用を目的としています。
母乳を促し、心の安定、産後鬱の予防に役立つ栄養価の高いハーブのブレンドです。産後の数か月はホルモンのバランスが急激に変化する時期ですし、育児や赤ちゃんを迎えた新生活に対する不安や悩みでお母さんの心と体はとてもデリケートです。
穏やかな気持ちで授乳ができると様々なホルモンが刺激され、母体の回復を早め、母性の確立や心の安定、至福感が得られ、赤ちゃんの健全な心と体の発育が促され、母子の結びつきは強まる、するとさらに催乳作用が働くという好循環をもたらします。
直接の授乳が適わなず搾乳されている方の心身ストレスの軽減、母乳の量が減ってきてしまったかな?という方にも最適です。
また、ボンディングに含まれているハーブには血糖値をコントロールする働きがあります。プロセスの使用に適合しない方はお試し下さい。
note
❥ 糖尿病治療薬をご使用中の方は血糖値をさらに下げる可能性があります。医師とご相談の上ご使用下さい(フェネグリーク、ゴーツルー、ネトル)
❥ 妊娠中の方のご使用はお勧めいたしません (フェヌグリーク)
(毎回よく混ぜてから掬って下さい)
![]() 抽出時間は 3分〜8分、お好みですが長いほど成分がより多く抽出されます
抽出時間は 3分〜8分、お好みですが長いほど成分がより多く抽出されます
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます
原材料
フェネル Foeniculum vulgare (認定オーガニック エジプト)
フェヌグリーク Trigonella foenum-graecum (認定オーガニック エジプト)
ルイボス Aspalathus linearis (認定オーガニック 南アフリカ)
ダンデライオンルート Taraxacum officinalis (認定オーガニック ドイツ)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
ゴーツルー Galega officinalis (認定オーガニック ハンガリー)
リンデン Tilia Spp (認定オーガニック ポーランド)
ネトル Urtica dioica (認定オーガニック エジプト)
アニシード Pimpinella anisum (認定オーガニック エジプト)
Process プロセス 糖の代謝と糖化対策
プロセスは血糖値急上昇の抑制を目指し、膵臓の細胞を元気にしてインシュリン機能を整える、小腸で吸収される糖の量を抑える、筋肉に取り込まれる糖の量を増やす、肝臓で糖が再成されるのを防ぐ、といった目的のハーブを配合してします。
食後の血糖値の急上昇が続くと太りやすくて痩せにくい体質を助長したり、糖化によるAGE*を誘発して肌や髪、骨や爪が老化・劣化したり、脳や血管など全身の細胞の損傷を招いて生活習慣病(糖尿病、脳血管疾患、ガン、心臓病、肥満症、動脈硬化症や高血圧症など)の原因となります。
生活習慣病の予防やアンチエイジング対策を始めたい、ダイエットや運動をしているのにちっとも減量しない、おなかがすくとイライラしてしまう、常時または生理前に甘いものへの強い欲求が抑えられない、という方々にお勧めです。
Processの飲用に適わない方は、似た穏やかな働きが期待できるBonding ボンディング (マム&ベビーシリーズ)をお試しください。
AGE*(終末糖化産物)とは、糖がタンパク質と結びついて変性を起こす糖化反応によって作られる物質です。タンパク質の劣化や老化(硬化、繊維化、色素沈着)、活性酸素の発生という?強い毒性物質です。血糖値が急上昇すると長時間処理しきれない多くの糖分が血中に浮遊して細胞(タンパク質)との接触チャンスが増加し、糖化が進んでAGEの生成が加速されます。
Note
❥ ステビアアレルギーのある方はご注意ください
❥ 妊娠中、授乳中の方のご使用はお勧めできません
❥ 糖尿病治療薬との併用は相乗効果がありますのでご注意下さい。
❥ミネラルサプリメントをご使用の方は吸収阻害のリスクがありますのでご注意下さい (ギムネマ)。
❥ 出血性疾患、胆石、胃潰瘍、逆流性食道炎のある方、心臓病薬、抗凝血剤などをお使いの方は医師と
ご相談の上ご使用下さい。
(毎回よく混ぜてから掬って下さい)
![]() 1日1〜3杯 を目安に 食前、空腹時、または甘いものを我慢したい時などに召し上がると効果的です。
1日1〜3杯 を目安に 食前、空腹時、または甘いものを我慢したい時などに召し上がると効果的です。
§ ホットがお勧めです。胃に温かい満足感が得られ、食欲や甘いものへの欲求を抑えてくれます。
原材料
ギムネマ Gymnema silvestre (認定オーガニック インド)
ゴーツルー Galega officinalis (認定オーガニック ハンガリー)
ステビアリーフ Stevia rebaudiana ? (認定オーガニック パラグアイ)
フェヌグリーク Trigonella foenum-graecum (認定オーガニック エジプト)
ルイボス Aspalathus linearis (認定オーガニック 南アフリカ)
コドノプシス Codonopsis pilosula(ワイルドフラフト 中国)
ダンデライオンリーフ taraxcum off.Folia (認定オーガニック ハンガリー)
スペアミント Mentha spicata (認定オーガニック エジプト)
コーンシルク Zea mays (ワイルドクラフト ハンガリー)
モナルダ Monarda fistulosa (認定オーガニック USA)
オリーブリーフ Olea europaea (認定オーガニック クロアチア)
ホーソン Crataegus monogyna (認定オーガニック ドイツ)
ジンジャー Zingiber officinale(認定オーガニック ネパール)
ローズヒップ Rosa canina (認定オーガニック 南アフリカ)
Tension テンション キレイな血管
テンションはつるつるっとした血管の中をスムーズに血液が流れている、そんな理想的な状態を目指し、脂代謝のコントロールを助けるハーブ、抗酸化作用で血中脂質の酸化を防ぐハーブ、血管を丈夫にするハーブ、心身リラックスで血管を広げるハーブ、血圧を安定させるハーブ、血行を促進するハーブを配合しました。
血管壁に脂汚れが付くと血管は詰まりやすくなったり血圧が高まったり、同時に細胞が変性して弾力を失い硬く脆くなります。またストレスなどで血管が収縮したりするとさらにリスクは高まります。血の巡りが悪いと脳から爪先まで様々な症状が現れるだけでなく、命に係わる脳・心臓血管系の病気につながることはいうまでもありません。未病のうちの予防対策を。
Note
❥ 妊娠中の方(ドンカイ、ヤロウ)、出血性疾患(レッドセージ)のある方は使用を避けて下さい
❥ 胆石、胃潰瘍や逆流性食道炎のある方(ジンジャー)、心臓病薬(ホーソン)、降圧剤(レッドセージ、オリーブリーフ)、抗凝固剤(ギンコ、ドンカイ、ジンジャー)との併用は効果を高めるリスク、免疫抑制剤やステロイド剤(アストラガルス)は効果が減価するリスクがありますので医師とご相談のうえご使用ください。
![]() 使用量 1杯分(180ml)に対してスプーン1杯(毎回よく混ぜてから掬って下さい)
使用量 1杯分(180ml)に対してスプーン1杯(毎回よく混ぜてから掬って下さい)
∞ 蜂蜜を加えたり冷やしても美味しく召し上がれます。
原材料
リンデン Tillia sp. (オーガニック ポーランド)
レッドセージ(ダンシェン)Salvia miltiorrhiza (コンベンショナル 中国)
アストラガルス Astragalus membranceus (認定 オーガニック 中国)
ヤロウ Achillea millefolium (認定オーガニック オーストラリア)
ドンカイ Angelica sinensis (認定オーガニック 中国)
オリーブリーフ Olea europaea (認定オーガニック クロアチア)
ホーソン Crataegus monogyna (認定オーガニック ドイツ)
ルイボス Aspalathus linearis (認定オーガニック 南アフリカ)
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
ジンジャー Zingiber officinale(認定オーガニック ネパール)
memo:
血管の壁に脂汚れがこびりつくと血管が硬くなって(動脈硬化)血液の通りがスムーズでなくなり、血圧の上昇を招いたり(高血圧症)、汚れの塊(血栓)が血管を詰まらせたり(脳梗塞、肺栓塞、心筋梗塞などの虚血性心疾患や心不全)、傷ついて弱った箇所が薄くなると裂けたり破けたり(脳出血)、一部だけ膨らんで瘤(動脈瘤、静脈瘤)を作ったりします。心疾患は日本における死因の第2位であり、脳血管疾患は第3位です。脳梗塞や脳出血で障害を受けた部位によっては認知機能が低下したり言語的なコミュニケーションが困難になることもありますし、脳の血行障害は認知症の発症リスクを高めてしまったりと生活の質(QOL)にも大きく影響します。
こういった生活習慣病は月経がある間の女性、つまりエストロゲンの働きに守られている間は男性よりもずっと罹病率が少ないのですが、閉経を迎えた途端に男性に一気に追いついて追い越してしまいますので更年期前後からの注意が必要です。
Tingle ティングル キリキリッ胃痛
空腹時やストレスに晒されている時に急に胃がキリキリッと痛くなる方、飲みすぎ食べ過ぎが続いて胃が荒れている、神経性の食欲不振、という時の為のお茶です。過剰な胃酸分泌を抑制、胃粘膜の保護するとともに胃の血流を改善、ストレス緩和といった働きを持つハーブを配合しています。これは胃酸の分泌に密接に関連している自律神経にアプローチすることで、辛い症状が徐々に緩和されより早い改善をサポートします。スリッパリーエルム、メドウスィート、マーシュマロウの粘質成分が空腹時の胃粘膜に優しく広がり保護しますので、空腹時の痛む前に召し上がるとこをお勧めします。特にスリッパリーエルムの樹皮に含まれる粘液質成分には毒素の分解、細胞膜の保護といった作用とともに炎症や痛みを抑制しますので潰瘍の予防にも働きます。過敏症の胃腸にも安全です。
喉がイガイガする時にもお勧めです。特に蜂蜜と一緒に摂るとより効果的です。
♣ 胃がキリキリ痛む症状は重篤な疾病が隠れている場合がります。
急性の場合はもちろん、慢性的に続く場合は先ず受診してください。その際、ピロリ菌の検査を是非申し出ることをお勧めします。
♥ 食後の症状、消化不良の不快症状の予防や緩和にはCosy, Crispyがおすすめです。
Note*
❥ キク科の植物にアレルギーのある方はご注意ください(カモマイル)
❥ 処方薬やサプリメントを服用中の方は少なくとも2時間以上開けて召し上がって下さい(スリパリーエルム)
❥ 降圧剤、心臓病薬、ステロイド剤、免疫抑制剤をお使いの方はご注意下さい。(リコリス)
❥ 妊娠中の方、高血圧症の方、心臓病のある方は多量多飲を避けて下さい。(リコリス)
(毎回よく混ぜてから掬って下さい)
![]() 抽出時間は 5分〜10分、お好みですが長いほど成分がより多く抽出されます
抽出時間は 5分〜10分、お好みですが長いほど成分がより多く抽出されます
*カップに注ぐ際、粗めの茶漉しを使ってスリッパリーエルム(ベージュ色の粉)の粘質成分を漉し取らずに一緒に摂取ようにして下さい。
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
ただし糖(蜂蜜)はピロリ菌の大好物です。ピロリ菌を保菌している方は糖分の摂取を避けて下さい。
原材料
スリパリーエルムパウダー Ulmus rubra (認定オーガニック USA)
メドウスィート Filipendula ulmaria (認定オーガニック ハンガリー)
マーシュマロウ Althea officinalis (認定オーガニック クロアチア)
リコリス根 Glycyrrhiza glabra (認定オーガニック イタリー)
オレンジピール Citrus riticulata (認定オーガニック ガーナ)
ペパーミントMentha piperita (認定オーガニック エジプト)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
タイム Thymus vulgaris (認定オーガニック エジプト)
memo:
胃酸過多なのか胃酸欠乏なのか…まず受診をお勧めします
胸やけを伴うと胃酸過多、胃もたれを伴うと胃酸欠乏いわれますが、人にって両方の症状が出たり逆の症状が出る場合もありますので自己判断で胃薬を飲むのは逆効果になる場合もあります。胃や十二指腸の潰瘍、逆流性食道炎、胃ガンなどでも同じような症状があります。まず胃痛の症状がある方は受診して胃酸過多なのか、胃酸欠乏による消化不良なのか、ピロリ菌はいないか、重篤な病気ではないか、これら確認することをおすすめします。
Regular レギュラー 腸の環境を整える
腸は最大のデトックス器官⋯体の老廃物を最も多く排出してくれる器官です。腸のリズムと環境を整えて規則正しく排泄を促すことは、心身の健康維持と肌美容の基本となるセルフケアです。
レギュラーには強い緩下作用のあるハーブは含まれておりませんので、腸の痙攣や痛みを起こす心配もなく腸の正常な機能を導くお茶です。肝機能を整え胆汁の分泌を促して腸の働きを向上させるハーブ、食物の消化、栄養素の吸収、老廃物の排泄を促進するハーブ、善玉菌の繁殖や腸の運動促進に有効なビタミンC豊富なハーブを配合しています。水分を含むと粘液質となるスリッパリーエルムが隅々にまで行き渡り、腸管を保護しながら宿便を一掃する役目も果たします。強い緩下剤を使う場合一緒に摂ると薬による痛みや渋りを予防できますし、便秘と下痢を繰り返してしまう方にもおすすめです。
また腸は最大の免疫器官でもあります。腸内環境が最適な状態に整っていれば、免疫力の低下や異常な免疫反応を防ぐことにつながります。*プロバイオティックスも一緒に摂るとさらに効果的です。
*プロバイオティックスとは 腸で有益な作用を発揮する微生物(乳酸菌、ビフィズス菌、糖化菌、納豆菌、酪酸菌、酵母菌など)を含む食品や製品を指します。
Note
❥ 妊娠中の方にはお勧めできません。(バードック、チコリールート)
❥ 他の薬やサプリメントとは少なくとも2時間以上開けて召し上がって下さい(スリパリーエルム、マーシュマロウ)
❥ 胆道閉鎖、胆嚢炎、腸閉塞、胆石のある方は医師とご相談の上ご使用下さい(ダンデライオンルート)
![]() 使用量 : 1杯分(180ml)に対して茶匙1杯 (毎回よく混ぜてから掬って下さい。)
使用量 : 1杯分(180ml)に対して茶匙1杯 (毎回よく混ぜてから掬って下さい。)
![]() 抽出時間は 5分〜10分を目安にお好みで
抽出時間は 5分〜10分を目安にお好みで
*カップに注ぐ際、粗めの茶漉しを使うと粘質成分も一緒に摂取できますのでより効果的です
∞ ホットでもアイスでも、蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
ダンデライオンルート(焙煎)Taraxcum off.radix (認定オーガニック ドイツ)
チコリールート(焙煎)Cichorium intybus (認定オーガニック ドイツ)
ダンデライオンリーフ Taraxacum officinalis (認定オーガニック ドイツ)
バードック Arctium lappa (認定オーガニック イタリー)
スリパリーエルムパウダー Ulmus rubra (認定オーガニック USA)
フェネル Foeniculum vulgare (認定オーガニック オーストラリア)
メドウスィートFilipendula ulmaria (認定オーガニック ハンガリー)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック. エジプト)
ローズヒップ Rosa canine (認定オーガニック 南アフリカ)
ハイビスカス Hibiscus sabdariffa (認定オーガニック、エジプト)
マーシュマロウ根 Althea officinalis (認定オーガニック クロアチア)
Reaction リアクション 過敏な粘膜症状に
季節の変わり目や気温変化、花粉やほこりに反応して起こるくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、喉のかゆみ、咳、目のかゆみや涙、といった不快なアレルギー性の症状の予防と改善を目指すお茶です。免疫力を調整するハーブ、アレルギー性反応を抑えるハーブ、粘膜の炎症やカタール症状を鎮めるハーブ、抗菌作用のあるハーブを配合。予防対策はマスク、うがい、洗顔と、症状が出る前からリアクションを飲み始めるのがコツです。抗ヒスタミン剤と併用しても安全です。鼻風邪の症状にもご利用ください。
Note*
❥ キク科の植物にアレルギーがある方はご注意下さい (エキナシア、カモマイル)
❥ 妊娠中の方は多量多飲をお控えください (バイカルスカルキャップ)
❥ インターフェロン治療中の方は医師とご相談の上ご使用ください(バイカルスカルキャップ)
❥ 抗凝固剤、アスピリン等をお使いの方は薬効を高める可能性がありますのでご注意下さい
(エキナシア、バイカルスカルキャップ)
❥ 他の薬剤やサプリメントとは2時間以上開けてご使用下さい (マーシュマロウ)
∞ ホットでもアイスでも, 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
まれに、花粉症のある方の中で蜂蜜アレルギーがある方がいらっしゃいますので蜂蜜のご使用にご注意下 さい。
原材料:
エキナシア根 Echinacea puraprea ( 認定オーガニック ドイツ)
アルビジア Albizia lebbek (ワイルトクラフト インド)
ネトル葉 Urtica dioica (認定オーガニック エジプト)
オレンジピール Citrus sinensis (認定オーガニック ガーナ)
アイブライト Euphrasia oggicinalis (ワイルドクラフト ポーランド)
バイカル・スカルキャップ Scutellaria baicalensis (ワイルドクラフト 中国)
ゴールデンロッドSolidago virgaurea (認定オーガニック オーストラリア)
エルダーフラワー Sambucus nigra (認定オーガニック ハンガリー)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
マーシュマロウ根 Althea officinalis (認定オーガニック クロアチア)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
タイム Thymus vulgaris (認定オーガニック エジプト)
Pillow ピロー 1日の終わりに
1日を穏やかな気持ちで閉じるひと時、ゆったりと1杯のPillow で過ごしてみてはいかがでしょう。穏やかに眠気を誘う作用のあるハーブとリラックス効果のあるハーブを中心に、自律神経を整えるハーブ、不安を鎮めるハーブ、睡眠の妨げとなる消化機能の不全を改善するハーブを配合しています。神経の緊張がほぐれ、体中の筋肉が緩み、呼吸や心拍を整い、気持ちを落ち着かせ、ゆったりと心地よい眠りに…
疲れているのに様々な思いが頭に散乱したり昼間のイライラを引きずっていたり、理由もないのに不安な気持ちがおさまらない・・・そんな時は明かりを落し、すべての電子機器と頭のスイッチをOFFにし、ピローで良い睡眠を取れる習慣をつけましょう。質の良い眠りは美容と健康の基本です。
♥ 昼間のイライラにはComfyをどうぞ。
Note*
❥ 妊娠中、授乳中の方は使用できません。(ジャマイカンドッグウッド、パッションフラワー)
❥ 眠気を催す作用のあるハーブを配合していますので、車や機械等の運転前のご使用は避けてください。
❥ 睡眠導入薬や睡眠薬、アルコール飲料との併用は効果が増大する可能性があるのでご注意下さい。
❥ キク科の植物にアレルギーのある方はご注意ください (カモマイル)
❥ 抗凝固剤をお使いの方はご注意下さい (カモマイル)
§ ホットで飲むことをお勧めします。
原材料
ジャマイカンドッグウッド 根の皮 Piscidia piscipula (慣行栽培 ジャマイカ)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
パッションフラワー Passiflora incarnata (認定オーガニック オーストラリア)
リンデンフラワー Tillia sp. (認定オーガニック ポーランド)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
ラベンダー Lavandula angustifolia (認定オーガニック オーストラリア)
Purify ピュリファイ 発汗と利尿作用で代謝アップ
入浴前やマッサージ前の1杯として楽しまれると効果的なお茶です。身も心もリラックスさせるハーブ、水分の代謝を促進するハーブ、発汗作用のあるハーブ、利尿作用を持つハーブ、リンパの流れを良くするハーブ、腎機能を促進するハーブなどなどをブレンドし、体液や血液の循環・代謝・浄化、排泄しやすい体を作ります。発汗は交感神を刺激するのでリラックスや多幸感が得られる効果もあり、肌のターンオーバーを促し美肌作りに欠かせません。飲みすぎた翌朝、むくみの解消、膀胱炎の予防にもお役立ていただけます。
Note
❥ 利尿作用がありますので他の利尿剤をお使いの方は併用をお控えください。
❥ 妊娠中の方のご使用はおすすめいたしません。(バードック、ヒソップ)
❥ 抗凝固剤(ワーファリン、アスピリンなど)服用の方は効果を高める作用がありますのでご注意下さい。(ジンジャー、エキナシア)。
§ ホットでどうぞ。
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
ダンデライオン・リーフ Taraxacum officinalis (認定オーガニック ハンガリー)
コーンシルク Zea mays (ワイルドクラフト ハンガリー)
レディースマントル Alchemilla vulgaris (ワイルドクラフト トルコ)
リンデンフラワー Tillia sp. (認定オーガニック ポーランド)
エキナシア根 Echinacea purpurea (認定オーガニック ドイツ)
カモマイル Matricaria chamomilla (認定オーガニック エジプト)
ゴールデンロッド Solidago virgaurea (認定オーガニック オーストラリア)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
ヒソップ Hyssopus officinalis (認定オーガニック オーストラリア)
キャットミント Nepeta cataria (認定オーガニック クロアチア)
エルダーフラワー Sambucus nigra (認定オーガニック ハンガリー)
バードック Arctium lappa (認定オーガニック イタリア)
| ? |
Guard ガード 抵抗力をサポート
疲れやストレス、体力の低下を感じる時は抵抗力も低下しています。ガードは病原菌の侵入を防いだり初期攻撃の段階で戦うあなたの抵抗力をバックアップします。免疫力向上のハーブと心身の耐久力アップのハーブ、免疫力に欠かせないビタミンCを豊富に含むハーブをブレンドしています。風邪やインフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症が流行る冬の対策に、また様々な疾患の予防と改善にお役立てください。1日3杯のガードと十分な休養・睡眠で体を守りましょう。
Note
❥ シナモンにアレルギーのある方はご注意ください
❥ 妊娠中の使用はお勧めできません (シナモン、バイカルスカルキャップ)
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用の方は効果を高める作用があるのでご注意ください。
(エキナシア、ジンジャー、バイカルスカルキャプ)
❥ 胃/十二指腸潰瘍のある方(シナモン)、胆石、逆流性食道炎のある方(ジンジャー)は医師とご相談の上ご使用下さい。
❥ インターフェロン治療中の方(バイカルスカルキャップ)は医師とご相談ください。
❥ 免疫疾患のある方、ステロイド剤、免疫抑制剤をご使用の方は免疫強化作用があるので避けて下さい。
(アストラガルス、エキナシア)
![]() 10分〜15分 これは根のお茶ですのでじっくり蒸らしてください。
10分〜15分 これは根のお茶ですのでじっくり蒸らしてください。
∞ 冷たくしたり蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
エキナシア根 Echinacea puraprea (認定 オーガニック ドイツ)
コドノプシス Codonopsis pilosula (コンベンショナル 中国)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
アストラガルス Astragalus membranaceous (認定オーガニック 中国)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
シナモン Cinnamomum cassia (認定オーガニック ベトナム)
ペオニー Paeonia lactiflora (コンベンショナル 中国)
ローズヒップ Rosa canina (認定オーガニック 南アフリカ)
ハイビスカス Hibiscus sabdariffa (オーガニック エジプト)
バイカルスカルキャプ Scutellaria baicalensis (コンベンショナル 中国)
フェネル Foeniculum vulgare (認定オーガニック オーストラリア)
Comfy コンフィー 心を鎮めるフラワーティー
強いストレスにさらされてイライラ!トゲトゲ!気持ちが波立っている時,ゆっくりと心の整理をしたい時に最適なフラワーティーです。リラックス効果で神経や筋肉の緊張をほぐす作用、情緒を穏やかに鎮めて安定させる作用、ストレスに対処・耐久する力を底上げしてくれるハーブを集めたらこんな素敵なお茶になりました。カップを手にして、どこか懐かしいような清楚な花の香と味をじっくり五感で味わって下さい。まわりに誰かカリカリ、イライラしている人をみつけたら、そっと一杯入れて差し上げてみましょ。
♥ 逆に落ちこみ気分をひき上げたい時はEnhance, お休み前にはPillowをどうぞ。
Note
❥ キク科の植物にアレルギーのある方はご注意ください (カモマイル)
❥ 妊娠中の方のご使用はお勧めしません。(ローズマリー)
∞ 蜂蜜を加えたり冷やしても美味しく召し上がれます。
原材料
ラベンダー Lavandula angustifolia (認定オーガニック オーストラリア)
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
カレンヂュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
エルダーフラワー Sanbucus nigra (認定オーガニック)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
コーンフラワー Centaurea cyanus (ワイルドクラフト アルバニア)
リンデン Tillia sp. (認定オーガニック ポーランド)
Period ピリオド ブルーな日も軽やかに
生理中のお腹や腰の重苦しさや、ひきつれるような痛み、下痢や便秘、沈みがちな気分・・・こんな時には温かいピリオドを。血行を促進ハーブ、経血をスムーズに排出させるハーブ、冷えを解消するハーブ、子宮や神経の痙攣を抑えるハーブ、整腸作用のあるハーブ、沈みがちな気持ちを支えるハーブがブレンドされています。毎月明るくスルーできますように・・・
♣ 出血量の異常や下腹部の痛みといった症状はなんらかの疾患や妊娠の可能性も疑われますので受診をお勧めします。
また、少量の着床出血を早めの生理と混同してしまう場合があります。ご注意ください。
♥ 貧血気味の時にはTenderテンダー、発育過程(ティーンエイジャー)の生理のお悩みにはGirlsガールズをお勧めします。
Note
❥ シナモン、カモマイルなどにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 妊娠の可能性のある方は必ず生理を確認してからご使用下さい。 (チェストベリー、ドンカイ、パッションフラワー)
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用の方は効果を高めるハーブが含まれていますのでご注意ください。(ギンコ、ドンカイ、ジンジャー)
❥ 炭酸リチウム剤(躁鬱病などの治療薬)をご使用の方は医師とご相談のうえご使用ください。(シャタヴァリ)
 使用量 1杯分(約180ml)に対してハーブ茶匙1杯
使用量 1杯分(約180ml)に対してハーブ茶匙1杯
🍵ホットでお召し上がりください。
∞蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます
原材料
チェストツリーベリー Vitex agnes-castus (認定オーガニック クロアチア)
シャタヴァリ Asparagus racemosa (認定オーガニック インド)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
レディースマントル Alchemilla vulgaris (ワイルドクラフト トルコ)
ドンカイ Angelica sinensis (認定オーガニック 中国)
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
ペオニー Paeonia lactiflora (ワイルドクラフト 中国)
クランプバーク Viburnum opulus (ワイルドクラフト インド)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
リコリス Glycyrrhiza glabra (認定オーガニック イタリア)
シナモン Cinnamomum cassia (認定オーガニック ベトナム)
パッションフラワー Passiflora incarnata (認定オーガニック オーストラリア)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
Pre meno プレメノ 40代になったら
40歳が見えてきたら始めたいハーブティーです。
個人差はありますが閉経までの数年は更年期前半戦、プレメノポーズ(ぺリメノポーズ)と呼ばれる時期になります。少しずつ女性ホルモンの低下に体がうまく折り合いを付けてくれるように自律神経を整えていきましょう。動悸や過呼吸、イライラしたり疲れやすかったり、異常な発汗、吐き気や食欲不振、下痢や便秘といった症状に対応するハーブ、心身のストレス対処を支えてくれるハーブをブレンドしています。
「その時」は急にやってくるわけではありません。毎月の生理が順調であってもホルモンのバランスは緩やかに変化し始めます。第二の変調期を快適に過ごすために、PreMeno で心と体のソフトランディングを目指しましょう。Classy やMorning もご一緒にどうぞ。
♠エストロゲン依存性疾患(子宮筋腫、乳腺症、子宮内膜症、乳ガン、子宮ガンなど)の心配がある方はガールズまたはポストメノをお勧めします。
Note
❥ 妊娠中の方のご使用は避けて下さい。(ドンカイ チェストベリー ヤロウ シサンドラ)
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用の方は効果を高める作用のあるハーブが含まれていますので、ご注意ください。(ギンコ、コドノプシス、ドンカイ)
❥ ステロイド剤、免疫抑制剤をお使いの方は医師とご相談ください (アストラガスル)
❥ 炭酸リチウム剤(躁鬱病等の治療薬)をご使用の方は医師とご相談ください(シャタヴァリ)
・チェストツリーは毎朝同じ時間帯の空腹時に飲むとより効果的です。1杯目は毎朝食前の同じ時間帯に召し上がることをお勧めします。
・妊娠を希望されている方、妊娠する可能性がある方は毎周期の低温期にのみ継続して召し上がることをお勧めします。
原材料
ドンカイ Angelica sinensis (認定オーガニック 中国)
チェストツリー Vitex agnes-castus (認定オーガニック クロアチア)
レディースマントル Alchemilla vulgaris (ワイルドクラフト トルコ)
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
シャタヴァリ Asparagus racemosa (認定オーガニック インド)
ローズペタル Rosa rugosa (認定オーガニック エジプト)
ラベンダー Lavandula officinalis (認定オーガニック オーストラリア)
アストラガルス Astragalus membranaceous (認定オーガニック 中国)
コドノプシス Codonopsis pilosula (ワイルドクラフト 中国)
シサンドラ Schisandra chinensis (認定オーガニック 中国)
Ladies レディース 20代30代の女性に
20代30代女性の美と心身の健康を支えるハーブティーです。社会的な活動と共に女性器官の機能が最も重要な年代です。ストレスにも影響を受けがちな心身のバランスとホルモン分泌を安定に導き、排卵や子宮の機能を整えて妊娠に向けた体調管理や、生理不順や生理周期に伴う生理前緊張症や月経困難症といったトラブル改善のお手伝いをします。 焙煎したタンポポとチコリーのコクのあるお茶は毎日のお茶として楽しんでいただけます。
♠ 強い鬱を伴うPMSのある方はご相談ください
♠ エストロゲン依存性疾患(子宮筋腫、乳腺症、子宮内膜症、乳ガン、子宮ガンなど)がご心配な方はガールズかポストメノをお勧めします。
Note
♦ 妊娠中の方のご使用は避けて下さい。(ドンカイ、チェツトツリー、ヤロウ、チコリー)
♦ 炭酸リチウム剤(躁鬱病などの治療薬)をお使いの方は医師とご相談のうえご使用ください。
♦ グルテンアレルギーのある方はご注意下さい(オーツストロー)
• 毎朝、朝食前の同じ時間帯に1杯目を飲むとチェストツリーの効果が発揮されやすくなります。
• 妊娠を希望中の方、妊娠の可能性のある方は、安全の為に低温期のみ継続して召し上がることをお勧めします。
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
チェストツリーベリー Vitex agnes-castus (認定オーガニック クロアチア)
シャタヴァリ Asparagus racemosa (認定オーガニック インド)
レディースマントル Alchemilla vulgaris (ワイルドクラフト トルコ)
ドンカイ Angelica sinensis (認定オーガニック 中国)
ペオニー Paeonia lactiflora (ワイルドクラフト 中国)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
コドノプシス Codonopsis pilosula (ワイルドクラフト 中国)
フェネルシード Foeniculum vulgare (認定オーガニック オーストラリア)
オーツ Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
ウィザニア Withania Somnifera (認定オーガニック インド)
ヤロウ Achillea millefolium (認定オーガニック オーストラリア)
焙煎タンポポ根 Taraxacum officinalis (認定オーガニック ドイツ)
焙煎チコリー根 Chicorium intybus (認定オーガニック ドイツ)
Girls ガールズ 思春期の女の子専用
初潮前後から成人するまでの発育途中、女の子の心と体は繊細でバランスを崩しがちです。Girls ガールズは生理不順や生理痛、生理周期に伴って起こるニキビや肌あれ、下痢や便秘、吐き気や食欲不振、そして不安定になりがちな心のケアを目指すお茶です。心身の健やかな成長を妨げることなくホルモンバランスをととのえていきます。安心してお召し上がりください。
Note
❥カモマイルアレルギーのある方はご注意ください
❥妊娠中のご使用は避けて下さい(ローズマリー、パッションフラワー)
❥血圧症の方、心臓病のある方は多量摂取を控えてください。(リコリス)
∞蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
ペオニー Paeonia lactiflora (ワイルドクラフト 中国)
リコリス Glycyrrhiza glabra (認定オーガニック イタリア)
ハイビスカス Hibiscus sabdariffa (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
パパヤリーフ Carica papaya (認定オーガニック )
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
レモンバーベナ ?Alousia triphylla (認定オーガニック エジプト)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
ローズバッズ Rosa rugosa (認定オーガニック エジプト)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
パッションフラワー Passiflora incarnata (認定オーガニック オーストラリア)
バニラパウダー ?Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
Kid’s Tummy キッズタミー キッズの消化を助ける
2歳から12歳までのお子様用のお茶です。お子様は消化機能も未熟な上、ついはしゃいだり気分のノリがよいと食べ過ぎては消化不良を起こしがちです。Kid’s Tummyキッズタミーは、順調な消化を促して栄養の吸収を高め、消化不良によるおなかの張り、胸焼け、吐き気、下痢といった胃腸の不快症状を予防・緩和、胃腸の粘膜を保護するお子様用の食後のお茶です。お子様に適した穏やかな作用のハーブだけをブレンドし、バニラパウダーのほんのり甘い自然な風味で飲み易いお茶に仕上がっています。小さい時から食後は落ちついて食休みの時間を過ごす習慣をつけてあげましょう。もちろん、ご家族何方が飲んでも安心です。
♣お子様が激しく泣く時は重篤な疾患による場合があります。熱や顔色、体の変化や症状などを確かめて受診してください。
Note
❥ カモマイルにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 他の医薬品の吸収遅延を避けるため薬やサプリメントとは2時間以上開けてご使用下さい.(マーシュマロウ)
![]() 使用量 一杯分(約180cc)に対してハーブ茶匙1/2杯〜すりきり1杯
使用量 一杯分(約180cc)に対してハーブ茶匙1/2杯〜すりきり1杯
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
フェネル Foeniculum vulgare (認定オーガニック オーストラリア)
バニラ Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
マーシュマロウ Althea officinalis (認定オーガニック クロアチア)
Kid’s Pillow キッズピロー 眠れないキッズの為に
2歳から12歳のお子様用ベッドタイムティーです。お子様は来客や旅行、お出かけ、またテレビやゲーム、といったちょっとした事でも気持ちが昂ぶって眠れなくなってしまいます。 特に入園、入学、新学期、お引越しといった時期、新しい家族として下に赤ちゃんを迎えたりといった環境の変化がある時期は、健康な眠りに入りにくくなりがちです。 Kid’s Pillow キッズピローは幼い心と小さな体の緊張をやさしく解きほぐし、入眠の障害となる消化を助けて穏やかに眠りへと誘います。毎日続けても安全なお茶ですので規則正しい睡眠習慣をつけるためにお役立て下さい。
♣お子様が激しく泣く時は重篤な疾患による場合があります。熱や顔色、体の変化や症状などを確かめて受診してください。 ?
Note
❥ カモマイルにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 妊娠中のお母様のご使用はお勧めいたしません。(ヒソップ, パッションフラワー)
![]() 使用量 1杯(約180cc)に対してハーブ茶匙1/2杯~すりきり1杯
使用量 1杯(約180cc)に対してハーブ茶匙1/2杯~すりきり1杯
∞ミルクや蜂蜜を加えたり冷やしても、美味しく召し上がっていただけます。
原材料
リンデン Tillia sp. (認定オーガニック ポーランド)
キャットミント Nepeta cataria (認定オーガニック クロアチア)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
ヒソップ Hyssopus officinalis (認定オーガニック オーストラリア)
パッションフラワー Passiflora incarnata (認定オーガニック オーストラリア )
バニラパウダー Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
Lullaby ララバイ 赤ちゃんの穏やかな眠りに
授乳中のお母さんが召し上がることで母乳を通して赤ちゃんと二人で効果を共有でき、6か月以降の赤ちゃんには哺乳瓶で直接飲ませることができる安全なお茶です。
赤ちゃんにとっては毎日がはじめての体験や外界から受ける刺激にあふれています。これらは情操を養い知的発育や自我の形成に大切なものですが、神経の緊張や興奮が夜まで残るとなかなか寝付かれなかったり、突然夜泣きを始めたり…母さんも眠くて泣きたくなってしまいます。こんな時は「今日はたくさんのことを学んだんだね、これも知的な発育の過程」と考え、温かいララバイを2人で楽しんでみましょう。静かな環境でお母さんの優しい抱っこと Lullabyが穏やかな眠りに誘います。産後すぐから毎晩の習慣にして続けても安全なハーブのブレンドです。
♣ 赤ちゃんが激しくなく時は重篤な疾患がある場合があります。熱や顔色、体の変化などを確かめて医師の診察を受けてください。
Note
❥ カモマイルにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ お母さんが飲む場合、眠気を催す作用のあるハーブを配合していますので車や機械など運転前のご使用は避けてください。
・お母さんが飲む場合: 1杯分(約180cc)に対してハーブ茶匙すりきり1杯
・6か月以降の赤ちゃんが哺乳瓶で直接飲む場合:
1杯分(約180cc)に対してハーブ茶匙1/3杯〜2/3杯
♠1歳未満の赤ちゃんが直接飲む場合、蜂蜜を直接摂取することはできません。ご注意ください。
原材料
キャットミント Nepeta cataria (認定オーガニック クロアチア)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
リンデン Tillia sp. (認定オーガニック ポーランド)
バニラパウダー Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
Citrusy シトラシー レモン&ジンジャーティーで脳活性
勉強中、お仕事中の気分転換に最適なお茶です。レモン以上にレモンの芳香成分を含むレモンマートルを中心にレモン風味のハーブを集め、一つまみのジンジャーがアクセントになった究極のリフレッシュティーです。肩の力が抜けて気分もすっきり!レモンの香りには脳の働きを活性化し、とくに創造力、発想力や記憶力も向上する働きがあります。また呼吸器の粘膜を緩和する働きがあるハーブを配合しているので、鼻水、鼻づまり、喉のイガイガでイラッとしている時にもどうぞ。
Note
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用の方は効果を高める作用があるご注意下さい。(ジンジャー)
❥ 胆石のある方、胃潰瘍、逆流性食道炎のある方は医師とご相談の上ご使用下さい。(ジンジャー)
∞ 蜂蜜やレモンスライスを加えたり、冷やしても美味しく召し上がっていただけます。
原材料
レモンマートル Backhousia citriodora (認定オーガニック オーストラリア)
レモングラス Cymbopogon citratus (認定オーガニック エジプト)
レモンバーベナ Alousia triphylla (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
モナルダ Monarda fistulosa (認定オーガニック USA)
レモンピール Citrus limon (認定オーガニック ガーナ)
ジンジャー Zingiber officinalis (認定オーガニック ネパール)
Post meno ポストメノ 生理終了を迎えたら
ポストメノは、生理が終了を迎えた更年期後半戦、そしてそれ以降の女性の健康サポートを目的にブレンドされています。女性ホルモンの低下の影響を受けて起こる様々なトラブルの予防やスタミナアップ、ストレス対処に対応するハーブを集めました。生理から解放されたらこれからはもっと自由な時間、より美しくより元気に過ごしましょう!!
♥ 女性の美容に欠かせないビタミンCたっぷりのクラッシー,更年期以降増える生活習慣病を予防するテンション、も合わせてお楽しみください。
♣ 更年期障害に似た症状は別な疾患も疑われますので異常を感じる場合は受診をお勧めします。
Note
❥ 心臓病薬(ジゴキシンなど)をお使いの方は医師とご相談の上ご使用下さい。(ホーソン)
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用の方は効果を高めるハーブが含まれていますのでご注意ください。(ギンコ)
❥ 免疫疾患のある方、免疫抑制剤をお使いの方は免疫力を向上させるハーブが含まれているのでご注意下さい。(アストラガルス)
❥ グルテンアレルギーのある方はご注意下さい。(オーツストロー)
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
内容
レディースマントル Alchemilla vulgaris (ワイルドクラフト トルコ)
シャタバリ Asparagus racemosa (認定オーガニック インド)
アストラガルス Astragalus membranaceous (認定オーガニック 中国)
ラベンダー Lavandula angustifolia (認定オーガニック オーストラリア)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
パッションフラワー Passiflora incarnata (認定オーガニック オーストラリア)
カレンデュラ Calendula officinalisv (認定オーガニック エジプト)
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
コドノプシス Codonopsis pilosula (ワイルドクラフト 中国)
シサンドラ Schisandra chinensis (認定オーガニック 中国)
セージ Salvia officinalis (認定オーガニック トルコ)
ペオニー Paeonia lactiflora (ワイルドクラフト 中国)
ホーソン Crataegus monogyna (認定オーガニック ドイツ)
memo:
閉経以降は自律神経のバランスの崩れから不眠、ほてり、鬱、動悸、胃腸の不調、頭痛、肩こり、血圧の上昇、軽い尿漏れ、心身の疲れといった多彩な身体症状に加えて、イライラ、なんとなく不安、自信の喪失、落ち込みを感じやすくなります。ちょうどこの時期は子供たちの独立、親の看取りなど家庭環境の変化から”空の巣症候群”と重なって更年期症状が強くなるケースも多くあります。
また女性ホルモンが一端を担っていた脳神経細胞の増殖や脳の血流、血中脂質のコントロールなどの働きが一気に低下する為、脳神経機能が鈍化して記憶力の低下や高脂血症、動脈硬化、心臓病、高血圧などのリスクが高まります。45歳までの心筋梗塞の発症率は圧倒的に男性が高いのですが、それ以降、女性が逆転してしまうのも女性ホルモン低下が要因となっているからです。
Crispy クリスピー キリッとミント系でリフレッシュ
ミントの香りあふれるクリスピーは清々しい味とキリッと切れのある舌触りで、煩雑な現実から空気の澄んだ別世界へあなたを一気にワープ!
3種類のミントとレモングラス、オレンジピール、カレンヂュラ、ブラックペッパーコーンのブレンドは気分転換はもちろん、上気道のイライラや軽い咳を鎮めたり、頭痛に対する穏やかな鎮痛作用もあります。
また、胃のムカつきを抑える作用や整腸作用、口臭予防にも効果があるので食後のお茶としても最適です。ハーブティーなど無縁という男性にも人気のお茶です。
もう少しミントがマイルドな方が好き、という方にはキッズタミーがお勧めです。
Note
❥ 授乳中の方は減乳の可能性がありますので多量多飲をお控えください。(ミント属のハーブ)
∞ 蜂蜜を加えたり冷やしても美味しく召し上がっていただけます。
原材料
ペパーミント ?Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
スペアミント Mentha spicata (認定オーガニック エジプト)
キャットミント Nepeta cataria (認定オーガニック クロアチア)
レモングラス Cymbopogon citratus (認定オーガニック エジプト)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
オレンジ・ピール Citrus sinensis (認定オーガニック ガーナ)
ブラックペッパーコーン Piper nigrum (認定オーガニック インド)
Liven Up ライブンアップ シニアに活力
シニアの脳と体の元気をサポートする為にブレンドされたお茶です。アルツハイマーの予防にも効果を発揮するギンコと認知機能を向上させるバコパを配合し、細胞を守る抗酸化作用、脳の毛細血管から全身の末梢血管の血行促進、心臓や消化器官の働きを補助、脳や神経細胞を活発化、心身のスタミナアップで全身の代謝を高めるハーブのブレンドです。食欲がない、元気がない、なんとなくぼんやりで記憶力の低下が気になる、何も楽しむ気分になれず笑顔がない、軽い尿漏れ、気分が沈みがち…そんなシニア世代の方、高齢者をバックアップ。ミネラルやビタミン豊富で利尿作用がないお茶ですので熱中症対策の水分補給にもご利用ください。心にも体にもイキイキ、明るい気分で1日1度は外へ出てみると何か楽しい発見があるかもしれませんよ!
Note
❥ 妊娠中の方が一緒に楽しむことはお勧めできません。(シサンドラ、ローズマリー)
原材料
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
バコパ Bacopa monniera (認定オーガニック インド)
ホーソン Crataegus monogyna (認定オーガニック ドイツ)
シサンドラ Schisandra chinensis (認定オーガニック 中国)
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
コドノプシス Codonopsis pilosula (ワイルドクラフト 中国)
ラベンダー Lavendula angustifolia (認定オーガニック オーストラリア)
レモングラス Cymbopogon citratus (認定オーガニック エジプト)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
レモンバーベナ Alousia triphylla (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
パパヤリーフ Carica papaya (認定オーガニック )
ローズヒップ Rosa canina (認定オーガニック 南アフリカ )
タイム Thymus vulgaris (認定オーガニック エジプト)
Kid’s Calm キッズカーム キッズをなだめたい時
2歳から12歳のお子様を対象にしたお茶です。子供は嬉しい事、楽しい事、悲しい事、不快な事、どれに遭遇しても興奮し過ぎてしまいがちです。泣きやまなくなったり、はしゃぎ過ぎたり、おちつきなく走り回ったり、逆に拗ねたりお落ち込んでしまったり・・・なだめすかしてもなかなか治まらない・・・そんな時はまずキッズカームを1杯。お子様の神経の昂ぶりを鎮めて心も体も穏やかに落ち着かせるのを助けます。イベントや旅行中などにもポットに入れて携帯しておくと便利です。小さいうちに公衆マナーを学ぶのも大事なことです。
♣ お子様が激しく泣く時は重篤な疾患による場合があります。熱や顔色、体の変化や症状などを確かめて受診してください。
Note
❥ カモマイルにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ グルテンアレルギーのある方はご注意下さい。
![]() 使用量 1杯(約180cc)に対してハーブ茶匙1/2からすりきり1杯
使用量 1杯(約180cc)に対してハーブ茶匙1/2からすりきり1杯
∞ミルクや蜂蜜を加えたり、冷やしても美味しく召し上がれます。
原材料
キャットミント Nepeta cataria (認定オーガニック クロアチア)
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
スペアミント Mentha spicata (認定オーガニック エジプト)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
バニラパウダー Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
Cosy コージー ノンカフェイン・チャイ
紅茶葉の代わりにビタミンやミネラル豊富で抗酸化作用が高いルイボス、肝臓保護や体内浄化にも働くタンポポ根とチコリの根を焙煎したものを贅沢に配合したチャイは,飲み応えのあるコクがありながらノンカフェインですのでお休み前でも安心して召し上がっていただけます。
甘い香りのエキゾチックなスパイスいっぱいのチャイは、リラックス効果とともに基礎代謝を向上させて暑い日も寒い日もエネルギーを保つ耐久力up、血行促進、体内温度up、体脂肪の燃焼効率アップ、美肌作りにも一役かうお茶です。風邪を引きそうな時、寒気・肩こり、体が重だるい、といった時に是非お勧めです。
またスパイスたちには胃腸を整える働きや血糖値の上昇を抑える働きもあるので食後のお茶にも最適です。ストレートでもミルクと煮ても美味しく召し上がれます。
♥ スパイスが苦手な冷え症の方にはWarmをどうぞ。
Note
❥ シナモンにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 妊娠中の方は多量多飲を避けてください(カルダモン、シナモン、チコリー、アニシード)
❥ 胆石のある方は医師とご相談の上ご使用下さい(ダンデライオンルート)
❥ 胃潰瘍や逆流性食道炎のある方、胆道閉鎖、胆嚢炎、腸閉塞のある方は医師とご相談ください(ジンジャー)
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用の方は効果を高める働きがありますのでご注意下さい(ジンジャー)
素材の自然な姿がかわいらしいお茶ですが、ゴロゴロしていてまんべんなく掬うのがむずかしい場合は
すり鉢、ミルやプロセッサーなどで細かく砕くと使いやすくなります。
∞ ホット/アイスでも、蜂蜜を入れても美味しく召し上がれます
*ミルク・チャイの作り方:
1.水を約200cc入れた小鍋にコージーをスプーン1杯加え、水分が 2/3程度になるまで煮詰めます。
2.お好みの分量の牛乳や豆乳、スキムミルクを加えフツフツしてきたら濾してカップに注ぎます。
*ストレート・チャイで飲む場合
◊ 水を入れた小鍋で煮詰める
または
![]() 抽出時間は約15分を目安にお好みで (もしくは、お好みの濃さになるまで煮立ててください)
抽出時間は約15分を目安にお好みで (もしくは、お好みの濃さになるまで煮立ててください)
原材料
フェネル Foeniculum vulgare (認定オーガニック オーストラリア)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
カルダモンシード Elettaria cardamomum (認定オーガニック インド)
シナモンチップ Cinnamomum cassia (認定オーガニック ベトナム)
クローブ Syzygium aromaticum (認定オーガニック インド)
スターアニス Illicium verum (認定オーガニック ベトナム)
アニシード Pimpinella anisum (認定オーガニック エジプト)
バニラパウダー Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
ピンクペッパー Schinus molle (コンベンショナル マダガスカル)
焙煎ダンデライオンルート Taraxacum officinalis (認定オーガニック ドイツ)
焙煎チコリールート Chicorium intybus (認定オーガニック ドイツ)
ルイボス Aspalathus linearis (認定オーガニック 南アフリカ)
memo:
冷えは万病の元
冷えは自律神経の失調を招き、頭痛、肩こり、耳鳴り、めまい、倦怠感、吐き気、イライラ、不眠、過呼吸、うつ、といった精神的症状を起こしたり、肌荒れ、血色不良、クマ、腹痛、便秘、下痢、生理不順、PMS、足のむくみ、そしてエネルギー燃焼が低下が太りやす体を作ります。
また人間の理想的な平熱は36.5〜37度といわれていますが、36度を下回ると白血球のバランスが悪くなり免疫力が30%も低下し、さまざまな病気の原因となります。体内温度をしっかり保つということは、暑い日には表皮から熱を発散させ、寒い日には体の芯、内臓の温度を維持しておくことが出来るのです。
冷えの原因は
冬の寒さや冷房ばかりではありません。夏の冷房や冷たいもののを摂り過ぎで冷えた内臓は、秋から冬までその冷えを抱え込んでしまいます。
またストレスによる血管が収縮や運動不足も低体温の原因となっています。
夏も冬もコージーで新陳代謝を活発に
夏の熱いコージーは発汗作用による体内の熱の放出で疲労回復やむくみの解消に働きます。また冷たい飲み物を摂りがちになったり冷房で体が冷えてしまった時に胃腸を温めて整え食欲不振などを解消してくれます。
冬の温かいコージーは、血行促進作用で手足の指先まで温めてくれますので冷え性や肩こりの方にも最適です。内臓の冷えで弱まってしまうの消化機能を助け、また肌の新陳代謝も活発にして血行不良による皮脂不足、異常乾燥の対策になります。
Classy クラッシー ルビー色のフラワーティー
バラの花びら、蕾、実、ハイビスカスとブルーマロウの花を贅沢にブレンドしたフラワーティーは、クレオパトラも愛した高貴な香りであなたを包み込み、呼吸や心拍を穏やかに整えリラックスへ導きます。さらに、コラーゲンの生成や免疫や抗酸化、血行促進、保湿、整腸に欠かせない成分、ビタミンやミネラル、ポリフェノールやクエン酸が豊富で、血行、保湿、整腸、デトックス、リラックス、疲労回復そして、アンチエイジング、美肌作りに役立つフラワーティーです。お口に広がる酸味は熱でも壊れないビタミンCの証。ローズヒップにはビタミンCを熱から守る酵素や栄養素を一緒に含みますので、熱に弱いビタミンCも壊さず細胞へ送り届けます。
Note
・特になし。
∞冷やしたり蜂蜜やレモンスライスを加えても美味しく召し上がれます。
原材料
ローズペタル Rosa rugosa (認定オーガニック エジプト)
ローズヒップ Rosa canina (認定オーガニック 南アフリカ)
ハイビスカス Hibiscus sabdariffa (認定オーガニック エジプト)
ローズバッズ Rosa centifolia (認定オーガニック イラン)
コーンフラワー Centaurea cyanus (ワイルドクラフト アルバニア)
バニラパウダー Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
Colicky コリッキー たそがれ泣きや疳の虫に
授乳中のお母さんが召し上がることで母乳を通して赤ちゃんと二人で効果を共有でき、6か月以降の赤ちゃんには哺乳瓶で直接飲ませることができる安全なお茶です。
夕暮れになると泣いたりぐずったりしてお母さんを困らせる「たそがれ泣き」、あやしても泣きやまない疳の虫、おしめも綺麗、おなかもいっぱいなのになぜ?夕方の一番忙しい時間にぐずられるとお母さんも泣きたくなってしまいます。これらは神経の刺激に対する処理がうまくできなかったり、消化が遅く胃が重い、お腹に溜まったガスが放出できない、といった不快感が赤ちゃんをぐずらせている原因の1つではないかと言われています。
こんな時は「これも赤ちゃんの神経や消化器官の発達段階の一つ」と考え、赤ちゃんと過ごすお茶の時間にしてみましょう。お茶を飲んだ後はしばらくはお腹を優しくなでたり、抱っこやおんぶでスキンシップを。産後すぐに始めていただけます。
♣赤ちゃんが激しくなく時は重篤な疾患がある場合があります。熱や顔色、体の変化などを確かめて医師の診察を受けてください。
Note
❥ カモマイルにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 他の医薬品の吸収遅延を避けるため薬やサプリメントとは2時間以上開けてご使用下さい。(マーシュマロウ)
・お母さんが飲む場合: 1杯分(約180cc)に対してハーブ茶匙1杯
・6か月以降の赤ちゃんが哺乳瓶で直接飲む場合:
1杯分(約180cc)に対してハーブ茶匙1/3杯〜2/3杯
♠ 1歳未満の赤ちゃんは蜂蜜を直接摂取することができませんのでご注意ください。
原材料
カモマイル Matricaria recutita (認定オーガニック エジプト)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
フェネル Foeniculum vulgare (認定オーガニック オーストラリア)
マーシュマロウ Althea officinalis (認定オーガニック クロアチア)
リンデンフラワー Tillia sp. (認定オーガニック ポーランド)
ルイボス Aspalathus linearis (認定オーガニック 南アフリカ)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
バニラパウダー Vanilla planifolia (認定オーガニック インド)
Morning モーニング 朝の細胞リフレッシュ
寝起きの脳と体を一気に覚醒させるモーニング、目が覚めたら朝一番に飲みたい1杯です。
クエン酸豊富なハーブと新陳代謝を高めるハーブが、脳から爪先まで体中の細胞エネルギー工場のスイッチオン!ベルトコンベアーが勢いよく回り始めれば、昨日の代謝で出てきた老廃物や毒素は呼気、腸、腎臓からの排泄ラインへ送り出され、新たに摂取する酸素や栄養素はダブつくことなくエネルギーの燃料として消費されやすくなります。このサイクルが整うと毎朝全身の細胞がリフレッシュされ、臓器や器官が最適な状態を保つようになり、つまりは自律神経の安定に繋がる基礎となります。
排泄除去⋯腸からの排泄は単に消化機能の一部出はないのです。腸は免疫機能を司ると同時に「第二の脳」といわれように神経機能の一部として働いています。
またデトックスの最大器官である大腸の臓器時間は午前5時から9時。この時間内に自然な排泄を導びく事が心身の健康と美容にとって理想なのです。
シャキッとすっきり、爽やかな一日をスタート!朝が弱い方、不定愁訴が続く方はお試しください。二日酔いの朝にも最適です。
Note
❥ 妊娠中の方のご使用はお勧めいたしません。(シサンドラ)
❥ グルテンアレルギーのある方はご注意下さい(オーツストロー)
❥ 高血圧症、心臓病のある方、心臓病薬、降圧剤、利尿剤、ステロイド剤をお使いの方(リコリス)、
❥ 胆石、胃潰瘍、逆流性食道炎のある方、抗凝固剤をお使いの方(ジンジャー)は医師とご相談の上ご使用下さい
∞ 蜂蜜を加えても美味しく召し上がれます。
原材料
スペアミント Mentha spicata (認定オーガニック エジプト)
ハイビスカス Hibiscus sabdariffa (認定オーガニック エジプト)
ローズヒップ Rosa canina (認定オーガニック 南アフリカ)
レモングラス Cymbopogon citratus (認定オーガニック エジプト)
リコリス Glycyrrhiza glabra (認定オーガニック イタリア)
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
タイム Thymus vulgaris (認定オーガニック エジプト)
シサンドラ Schisandra chinensis (認定オーガニック 中国)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
カルダモン Elettaria cardamomum (認定オーガニック インド)
カレンデュラ Calendula officinalis (認定オーガニック エジプト)
バードック Arctium lappa (認定オーガニック イタリア)
Enhance エンハンス 落ち込んだ時には
やる気が出ない、心も体もエネルギーが足りない、落ち込みから立ち直れない、がっかりな出来事や対人関係のトラブルで気持ちが弱くなってしまったり、これといった出来事があったわけでもないのに気分が晴れない、五月病、なんとなく憂鬱な季節の変わり目、雨の月曜日……そんな時はエンハンスがあなたを励まします。
神経伝達機能を向上させてストレス対処力を高め、へこんだ気分を引き上げてくれるハーブのブレンドです。早く心の元気と笑顔を取り戻すことができますように...
Note
❥ 妊娠中のご使用はお勧めできません。(ローズマリー シサンドラ)
❥グルテンアレルギーのある方はご注意下さい(オーツ)
❥ 抗鬱剤との併用は薬の効果を高める働きがありますのでご注意下さい (ラベンダー)
∞ 蜂蜜を加えたり冷やしても美味しく召し上がっていただけます
原材料
スペアミント Mentha spicata (認定オーガニック エジプト)
ペパーミント Mentha piperita (認定オーガニック エジプト)
ラベンダー Laveadula angustifolia (認定オーガニック オーストラリア)
レモンバーム Melissa officinalis (認定オーガニック ドイツ)
ローズマリー Rosmarinus officinalis (認定オーガニック エジプト)
オーツストロー Avena sativa (認定オーガニック オーストラリア)
シサンドラ Schisandra chinensis (認定オーガニック 中国)
ローズペタル Rosa centifolia (認定オーガニック パキスタン)
レモンバーベナ Alousia triphylla (認定オーガニック エジプト)
コドノプシス Codonopsis pilosula (ワイルドクラフト 中国)
Warm ウォーム 血行促進で体を温める
冬の寒い日はもちろん、夏のエアコンの中でも手足が冷たくなったり肩が凝ったりしがちです。また背筋がゾクゾクっと風邪の予感を感じたら?Warmウォームを1杯。末梢血管まで血行を促進するハーブと体の芯から温めるハーブのブレンドがあなたの体を芯から優しく温めます。リラックス効果はもちろん、基礎代謝率を向上、血行促進で内臓温度を上げて体脂肪の燃焼効率を高めてくれます。胃腸を整える働きがあるので食後のお茶にも最適です。
♥ スパイスがお好きな方はコージーもお試しください。
Note
❥ カモマイルにアレルギーのある方はご注意ください。
❥ 妊娠中の方(ローズマリー、ヤロウ、エルダー)、授乳中の方(セージ)のご使用はお勧めできません。
❥ 抗凝固剤(アスピリン、ワーファリンなど)をご使用のかたは効果を高める作用にご注意ください(ギンコ、ジンジャー)
❥ 胆石のある方、胃潰瘍、逆流性食道炎のある方は医師とご相談の上ご使用下さい。(ジンジャー)
∞ 蜂蜜やミルクを加えても美味しく召し上がれます。ホットでどうぞ。
原材料
ギンコ Ginkgo biloba (認定オーガニック 中国)
ジンジャー Zingiber officinale (認定オーガニック ネパール)
カモマイル Matricaria recutita(認定オーガニック エジプト)
ヤロウ Achillea millefolium (認定オーガニック オーストラリア)
エルダー Sambuccus nigra(認定オーガニック ハンガリー)
ネトル Urtica dioica (認定オーガニック エジプト)
ローズマリー Rosmarius officinalis (認定オーガニック エジプト)
シナモン Cinanamomum zeylanicum (認定オーガニック スリランカ)
リコリス Glycyrrhiza glabra (認定オーガニック イタリア)
memo:
冷えの原因は?
冷えの原因は冬の寒さや冷房ばかりではありません。夏の冷たいもののを摂り過ぎで冷えた内臓は、その時ばかりか秋から冬までその冷えを抱え込んでしまいます。ダイエットによる代謝低下、薄着、ハイヒール・窮屈な下着などのほか、ストレスによる血管が収縮したままになってしまうことも原因となります。また体の熱エネルギーは筋肉で作られます。運動不足で筋肉量が減ってしまうと熱エネルギーを作りにくくなり体が冷え、低体温の原因となっています。
そして一番大事なことは、冷えると自律神経(交感神経 と副交感神経)のバランスが崩れる、自律神経のバランスが崩れると体が冷える…とこの繰り返し、循環劇関係なのです。つまり体を温めれば自律神経のバランスが整ってくるのです。
冷えは万病のもと?
冷えると血管が収縮することにより慢性的に細胞の栄養不足や酸素低下状態となり、頭痛、肩こり、疲れ易い、体力がない、肌荒れ、血色不良、クマ、腹痛、便秘、下痢、生理不順、PMS、足のむくみ、そしてエネルギー燃焼が低下しますので太りやすくなってしまいます。そして身体的なトラブルばかりか自律神経失調による吐き気、イライラ、不眠、過呼吸、うつ、といった精神的症状まで起こります。また人間の理想的な平熱は36.5〜37度といわれていますが、36度を下回ると白血球のバランスが悪くなり免疫力が30%も低下するといわれいます。つまり冷えは万病のもとといっても過言ではないのです。
Mum & Baby Support Series
マム&ベビーサポート・シリーズは, 出産直後の授乳中のお母さんと6ヶ月から24ヶ月までの赤ちゃんを対象にしています。もちろんお子様から高齢者まで、どなたにも楽しんでいただけます。授乳中のお母さんが召し上がれば、母乳を通じて新生児の赤ちゃんに伝えることができますので、お母さんと赤ちゃん2人で同じ効果を感じる事が出来ます。
また赤ちゃんの体に適した作用と、飲みやすい味・香りをもつハーブだけを使用していますので、生後6ヶ月からは赤ちゃんに哺乳瓶で直接飲ませることができる安全なハーブティーです。
おむつは?お腹が減っていない?これらを確かめても泣きやまない、熱、痛がる、腫れている、赤い、吐く、下痢といった症状は、重篤な病気のサインである可能性もあります。直ちに医師の診察を受けてください。
12ヶ月以内の赤ちゃんに直接ハチミツを与えることは避けてください。
| Colicky コリッキー |
夕暮れになると泣いたりぐずってお母さんを困らせる「たそがれ泣き」… 神経や消化器官の発達段階の一つと考えられています。Colicky でお腹に溜まったガスの放出を促し、神経を穏やかに落ち着かせてみましょう。飲んだ後はお腹を優しくなでたり、しばらくは抱っこやおんぶでスキンシップをつづけることをお勧めします。 | 内容 フェネル、カモマイル、ジンジャー ペパーミント、メドウスィート、リンデン、ヤロウ |
50g ($ ) |
| Lullaby ララバイ |
赤ちゃんにとって、はじめての物や外界から受ける刺激は情操を養い、知的発育や自我の形成に大切です。しかし多くを学んだ日は神経の緊張や興奮が夜まで残り夜泣きをしてしまいます。そんな夜は静かな環境で優しく抱っこして Lullaby を含ませてあげましょう。 | 内容 キャットミント、カモマイル、レモンバーム、ヒソップ、バレリアン |
50g ($ ) |
Kids(2-12y.o) Support Series
キッズサポート・シリーズは 2歳から12歳のお子様のためのハーブティーです。安全にお子様に合った働きをするハーブだけを使用しています。ひとつまみのオーガニックバニラパウダーでおいしい魔法がかかったお茶達です。もちろんお子様からお年寄りまで安全にお楽しみいただけます。
泣きやまない、熱、吐き気、痛がる、下痢 等の症状は重篤な病気のサインである可能性もあります。直ちに医師の診察を受けてください。
| Kids’ Calm キッズカーム |
お子様は嬉しい事、楽しい事、悲しい事、不快な事、どれに遭遇しても興奮し過ぎてしまいがち。 Kids’ Calm は、神経の昂ぶりを鎮めて心も体も穏やかに落ち着かせてくれます。乗り物の中や旅行中にお勧めです。 | 内容 キャットミント、カモマイル、レモンバーム、バニラ、スペアミント、オート麦 |
50g ($ ) |
| Kids’ Pillow キッズピロー |
はしゃぎすぎたり、気持ちが昂ぶっていてなかなか眠れない夜は Kids’ Pillow。お子様の心と体の緊張をやさしく解きほぐし、入眠の障害となる消化を助け、心穏やかに眠りへと誘います。 | 内容 リンデン キャットミント、カモマイル、スカルキャップ、レモンバーム、バニラ |
50g ($ ) |
| Kids’ Tummy キッズタミー |
お子様にも食後は Kids’ Tummy で気分もお腹もゆっくりリラックスできる食休みをとる習慣を。順調な消化を促して栄養の吸収を高め、消化不良で起きる胃腸の不快症状を予防・緩和します。食べ過ぎてしまった日は特にお勧めします。 | 内容 ローズマリー、ヒソップ、バニラ、リンデン、ラベンダー、オーツ |
50g ($ ) |
Senior Support Series
シニアサポートシリーズは中年以降、高齢者の方々を対象に配合されたハーブティーです。いずれのハーブもビタミンミネラルが豊富、作用が穏やかですので安全に召し上がっていただけます。
疾患をお持ちの方やお薬を服用中の方は医師にご相談されるか、ご注文の前にこちらにご相談下さい。
また、処方薬やサプリメントはハーブティーに限らず紅茶や緑茶で飲み下すのは避け、必ずお水で飲みましょう。
| Liven Up ライブン・アップ |
なんとなくぼんやりしたり、記憶力の低下が気になったり、何も楽しむ気分になれず、気分が沈みがち…そんなシニア世代の方を元気づけるのが Liven Up。体と脳の血行を良くし細胞を活性化すると、心にも体にもイキイキと元気が出てきます。明るい気分で1日1度は外へ出てみると何か楽しい発見があるかもしれません! | 内容 ギンコ、ホーソン、シサンドラ、ローズマリー、コドノプシス、ラベンダー、カルダモン、レモングラス、カレンデュラ、レモンバーベナ、レモンバーム |
50g ($ ) |
Female Support Series
フィーメール・サポートシリーズは女性のためのハーブティーです。生理サイクルに影響を受ける女性の心と体のコンディションを整えるハーブが処方されています。ご自分のステージにあわせてお選び下さい。
| Girls’balance ガールズ・バランス (19歳以下の少女たちへ) |
初潮前後から成長期の心と体は繊細で、バランスを崩しがちです。 Girls’balance は健やかな成長を妨げないように、ホルモン様作用のないハーブだけを配合し、生理や心を安定させるようにデザインされています。安心してお召し上がりください。 | 内容 ペオニア、リコリス、ハイビスカス、メリッサ、レディースマントル、レモングラス、アニス、バニラ、ローズマリー、ローズバッズ、カレンデュラ、パッションフラワー、レモンバーベナ、カモマイル |
50g ($ ) |
| Ladies’ Balance レディース・バランス (20代30代の女性に) |
Ladies’ Balance は、20代30代女性の生理不順や生理前緊張症(鬱症状をのぞく)のお悩みに。ホルモンのバランスを調整していくハーブを配合しています。 毎朝食前の同じ時間帯、低温期のみ(生理1日目から排卵日まで)飲む事をお勧めします。生理痛には Period Ease を鬱をともなうPMSには禁忌です。ご相談下さい。 |
内容 チェストツリー、シナモン、アニス、ペオニア、カレンデュラ、ドンカイ、ヤロウ、リンデン、レディースマントル、レモンバーム、ギンコ、マロウ、レモンバーベナ、フェネル、レモンバーム、ローズペタル |
50g ($ ) |
| Pre Meno Balance プレメノ・バランス (40歳から生理ストップまで) |
閉経前の更年期前半戦、プレ・メノポーズと呼ばれる時期を対象にしています。その時は急にやってくるわけではありません。毎月の生理があってもホルモンのバランスは緩やかに変化し始めています。40代になったら、 Matures’ Balance で心と体のソフトランディングを目指し、第二の変調期を快適に過ごしましょう。 毎朝食前の同じ時間帯、低温期のみ(生理1日目から排卵日まで)飲む事をお勧めします。生理が停止した後は、Post Meno Balance を |
内容 チェストツリー、セージ、カレンデュラ、レディースマントル、ホーソン、ギンコ、オーツ、レモンバーベナ、メリッサ、ネトル、ドンカイ、ローズペタル、ラベンダー、アストラガルス、ペパーミント、コドノプシス、シサンドラ |
50g ($ ) |
| Post Meno Balance ポストメノバランシング (生理停止後) |
更年期の後半戦です。不眠、ほてり、イライラ、胃腸の不快感、頭痛、肩こり、血圧の上昇、なんとなく心身の疲れ、といった多彩な不快症状が現れて不安を感じる時期です。受診しても疾患が見つからない時には PostMeno Balance。これからのより自由な時間を、より美しく、より元気に楽しむために、心と体も進化系に。 鬱や強い症状などでお悩みの場合はご相談下さい。 |
内容 ドンカイ、アストラガルス、ラベンダー、ペオニー、セージ、コドノプシス、カモマイル、アニス、ホーソン、ヤロウ、ギンコ、パッションフラワー、レモンバーベナ、オーツ |
50g ($ ) |
| Period Ease ピリオド イーズ |
生理中、お腹や腰が重かったり、ひき攣れるように痛むと、気分まで重くなりがち。受診しても疾患がない場合はPeriod Ease。血行促進、子宮や神経の痙攣の緩和などの働きで、この数日の辛さを軽減しましょう。 生理予定の数日前から飲み始めると効果的です。 |
内容 ドンカイ、シサンドラ、レディースマントル、カレンヂュラ、ペオニー、シナモン、クランプバーク、ペッパーミント、ギンコ、カモマイル、ラベンダー |
50g ($ ) |
Body, Mind and Energy Series
ボディー、マインド アンドエナジーシリーズは、あなたの心と体とエネルギーのバランスを調整するお手伝いをするハーブティーです。時間帯やあなたの気分、コンディションに合わせてお選び下さい。
| Morning モーニング |
朝は頭の先から爪先まで Morning で全身の細胞にエンジンをかけましょう。心も体もすっきりと目覚め、新しい一日を爽やか気分でスタートしましょう。 | 内容 ペパーミント、レモングラス、リコリス、ローズマリー 、タイム、ジンジャー、カルダモン |
50g ($ ) |
| Enhance エンハンス |
憂鬱、気持ちが塞ぐ、やる気が出ない、心も体もエネルギーが足りない、落ち込みから立ち直れない…そんな時は1杯の Enhance が、あなたが笑顔を取り戻すきっかけを与えてくれるでしょう。 | 内容 スペアミント、レモンバーム、オーツ、ラベンダ-、シサンドラ、タイム、セージ、コドノプシス |
50g ($ ) |
| Calm-A (anxious) カームA |
何か心配、ドキドキそわそわ落ち着かない、神経がぴりぴり緊張する、そんな時 Calm-A の香りと優しい味と薬効が、あなたの不安な心を包み込んで落ち着かせてくれるでしょう。 | 内容 ローズマリー、ヒソップ、バニラ、リンデン、ラベンダー、オーツ |
50g ($ ) |
| Calm-I (irritation) カームI |
イライラしたりカーッとなったり、気分を害されたり、ショックな出来事に遭遇してしまった時は、まずは深呼吸して Calm-I を一杯。心の荒波を鎮め、冷静なあなたを取り戻しましょう。 | 内容 カモマイル、スカルキャップ、ヒソップ、レモンバーム、レモンバーベナ、リンデン |
50g ($ ) |
| Warm ウォーム |
冬の寒い日や夏のエアコンの中で手足が冷たくなったり肩が凝ったり、また背筋がゾクゾクっと風邪の予感を感じたら Warm。血行を良くして、あなたの体を芯から優しく温める一杯です。 | 内容 ギンコ、シナモン、ジンジャー、アニス、カレンデュラ、オレンジピール、フェネル |
50g ($ ) |
| Pillow ピロー |
一日の終わりにそっとあなたのスイッチをオフに する Pillow。心と体の緊張を解きほぐしてリラックス。心地よく“眠りに入る”お手伝いをするお茶ですので翌朝に響くこともありません。 (眠気を誘う作用がありますので、服用後に運転などはしないで下さい) |
内容 カモマイル、リンデン、キャットニップ、パッションフラワー、バレリアン、カリフォルニアポピー、レモンバーム、ローズバッズピンク |
50g ($ ) |
| Smart スマート |
何となくボーっとする、集中できない、霞がかかったようで考えがまとまらない、特にお昼過ぎに感じませんか? Smart でティーブレイク。脳の血流を改善して冴えた頭を取り戻しましょう。 | 内容 ギンコ、シサンドラ、ローズマリー、ラベンダー、スペアミント、セージ |
50g ($ ) |
| Tummy タミー |
食後は Tummy で食休み。スッキリとした味わいで順調な消化を助け、食べ過ぎや脂っこい食事の後の胃もたれを防ぎます。(CシリーズのCosyもお勧めです) | 内容 タイム、ペパーミント、カモマイル、ヤロウ、オレンジピール、ジンジャー、レモングラス、フェネル、レモンバーベナ |
50g ($ ) |
| React リアクト |
季候の変化が引き金になる鼻、目、喉のムズムズやズルズル、イライラ、肌のかゆみなどに React。免疫機能を調整し過剰反応や炎症を抑えるハーブの配合です。予感がしたら早めに飲み始めておく事がコツです。 | 内容 アルビジア、アイブライト、アストラガルス、ネトル、エキナシア、エルダー、カモマイル、ゴールデンロッド、スカルキャップ |
50g ($ ) |
| Gripe グライプ |
胃のあたりにキュー、キリキリっとくる痛み、まず受診する事が大切です。未病、予防には Gripe。心配事やストレスで収縮する神経と胃のリラックス、胃の粘膜保護と痛みの緩和に働くハーブの処方です。 空腹時(食間)に飲むのが効果的です。 |
内容 レモンバーム、レモンバーベナ、ペオニア、マーシュマロウ、シナモン、カモマイル、キャットミント、リコリス |
50g ($ ) |
| Bad Sign バッドサイン |
くしゃみ、鼻水、喉痛、悪寒 、頭痛・・・風邪かな?という症状に気づいたらすぐに Bad Sign。風邪と戦う力を整え、体を温め、敵の攻撃が小さい段階で食い止めるのを助けます。1日3杯飲んで、よく休みましょう。 Warm もおすすめです。 | 内容 エキナシア、アストラガルス、ジンジャー、カモマイル、ネトル、エルダー、リンデン、タイム、セージ、ハイビスカス、レモングラス、ローズヒップ |
50g ($ ) |
FanC Series
ファンシー・シリーズは気分に合わせていつでも召し上がっていただけます。いずれもリラックス効果があっても眠気作用のないハーブを使用しておりますので、素敵な味わいと香りをお仕事中でも夜でもお楽しみいただけます。お気に召すまま、お選び下さい。
| Cosy コージー |
甘みのある豊かなスパイスの香りは、あなたを暖かく包み込む、居心地のよい隠れ家へと運んでくれます。深い味わいをお楽しみ下さい。食後のお茶にも最適です。 | 内容 フェネル、シナモン、ベルガモット、アップルバイト、スターアニス、カルダモン、クローブ、バニラ |
50g ($ ) |
| Crispy クリスピー |
このミントの香りあふれるお茶は、煩雑な現実から、空気のキリッと澄んだ別世界へとワープさせてくれます。爽快な香りと清々しい味、切れのある舌触りで気分を切り替えましょう。 | 内容 ペパーミント、スペアミント、キャットミント、オレンジピール |
50g ($ ) |
| Classy クラッシー |
まずは、この魅力的な茶葉が目を楽しませてくれると同時に呼吸も心拍も穏やかに。またさっぱりとした酸味は熱でも壊れないビタミンCの証です。高貴な香りに満たされてプリンセス気分をどうぞ。 | 内容 ローズバッス、ローズペタル、ローズヒップ、ハイビスカス、ブルーマロウ、ラベンダー、ホーソンベリー |
50g ($ ) |
| Citrusy シトラシー |
レモンの香りと風味で究極のリフレッシュ。気だるい気分を一掃し、脳もシャキッとクリアに。集中力と発想力を高め、明るく知的なあなたに戻してくれるでしょう。 | 内容 レモングラス、レモンバーベナ、レモンバーム、ベルガモット |
50g ($ ) |
| Comfy コンフィー |
情緒を穏やかに安定させる効果の高いお花を集めたら、こんな素敵なお茶になりました。さあ、カップを手にして、野に咲く草花の清楚な香りと味をじっくり五感で味わって下さい。 | 内容 ラベンダー、ローズマリー、カレンヂュラ、エルダー、カモマイル、ブルーマロウ、リンデン |
50g ($ ) |